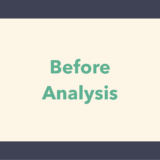今の世の中では、パワハラと言われることも、十数年前では当たり前に横行していました。それに精神疾患という認識もまだ世間的に認知されていない時だったので、相当に苦しい思いを人はたくさんいたと思います。
その反動なのか、最近、部下を褒めましょう!というマネジメントが正しいという論調が増えてきているように思います。
アルフレッド・アドラーの心理学が注目されはじめたことが背景にあると憶測しています。自己肯定を促す内容であり現代に受け入れやすい心理学です。
アドラーの心理学は、私も好きで数冊読んでいますが、なんだか、それだけではうまく機能しないような違和感を覚えています。
もちろん心理学なので、正解があるわけではないのですが、企業でのマネジメントにおいては、ある程度最適な対応があると考えています。
褒めるマネジメントがもたらす良い効果、悪い効果があります。褒めると自信がつく!褒めると「調子に乗る」!これを「マネジメントの褒めジレンマ」と呼ぶことにします。
「マネジメントの褒めジレンマ」を解消する方法を紹介してきます。
目次
褒めるマネジメント
褒めるマネジメントがもたらす良い効果

メンバーを褒めることがもたらす良い効果から考えていきます。
怒られるより、褒められる方が嬉しいのは誰しも間違いないと思います。よっぽど偏屈な人でない限り、褒められると嬉しいです。
gyakuメンバーを嬉しい気分にさせることの効果ということになります。
- やる気が高まる
- 仕事が楽しくなる
- 仕事への満足度があがる
- 挑戦意欲がたかまる
- 自信がつく
自信がつき、やる気が高まる、満足度が上がって、積極性が出てくるので、良い循環に入り、成長が加速する効果もあります。
CMで「やる気スイッチ」というのがありましたが、褒めることが一つの「やる気スイッチ」になっている人もいると思います。
メンバーは気持ちよく仕事ができ、上司との関係も良好な状況をになります。
褒めるマネジメントがもたらす悪い効果

褒めることには良いことしかないのか?というと、そんなことはありません。
感覚的な表現を使うと「調子に乗る」ことが悪い効果となります。その「調子に乗る」となにが問題なのでしょうか?
褒められる事が良い効果をもたらすことは先ほどお話しましたが、いいことづくめでした。逆に悪い効果をもたらしてしまう「調子に乗る」状態を具体的な状態で表現すると以下のようになります。
- 手抜きをする
- 不注意になる
- 雑になる
- 仕事をこなすようになる
- 向上心が低下する
このような状態を「調子に乗る」という表現を、悪い意味で使っているのではないでしょうか?
「これくらいできていれば、前に褒められたから、これくらいでいいだろう」という気持ちが発生し、それが手抜きや不注意さ、雑な仕事にしてしまいます。褒められた時よりもアウトプットの質が下がってしまう状態です。
また、仕事を楽しまなくなってしまいますし、向上心が低下します。褒められることに満足をしているので、同じレベルのアウトプットを続けようとして、前回と同じくらい時間をかけて、同じくらいのレベルの仕事をしていれば、褒められると思ってしまうからです。
では、良い効果と悪い効果になってしまう違いはなにが原因なのでしょうか?良い効果は発揮して欲しいから、褒めたいけど、調子に乗られると逆効果だから、褒めない?いや、効果的に褒めることは意図的に使った方がいいです。
褒めるマネジメントの効果が逆転する原因

褒めることが影響する人間の心理が原因です。
非常にシンプルなことなのですが、褒められると人は気持ちよくなり、自信がつきます。褒めることで良い効果は本質的には「自信がつく」ことにあります。
「自信がつく」ことで、ポジティブになり、考え方が苦難を乗り越えることを考え、行動は早く、強くなります。これらのことは、自信がついた事の副次的な効果としてあらわれているに過ぎません。
では、悪い効果のほうは「過信」になる事です。悪い効果は全て「過信」から来ます。過信して、できると思っているから、手を抜いたり、不注意になったり、雑になります。向上心が低下するのも過信しているので、これ以上は求められていないと勘違いするからです。
マネジメントの褒めジレンマ
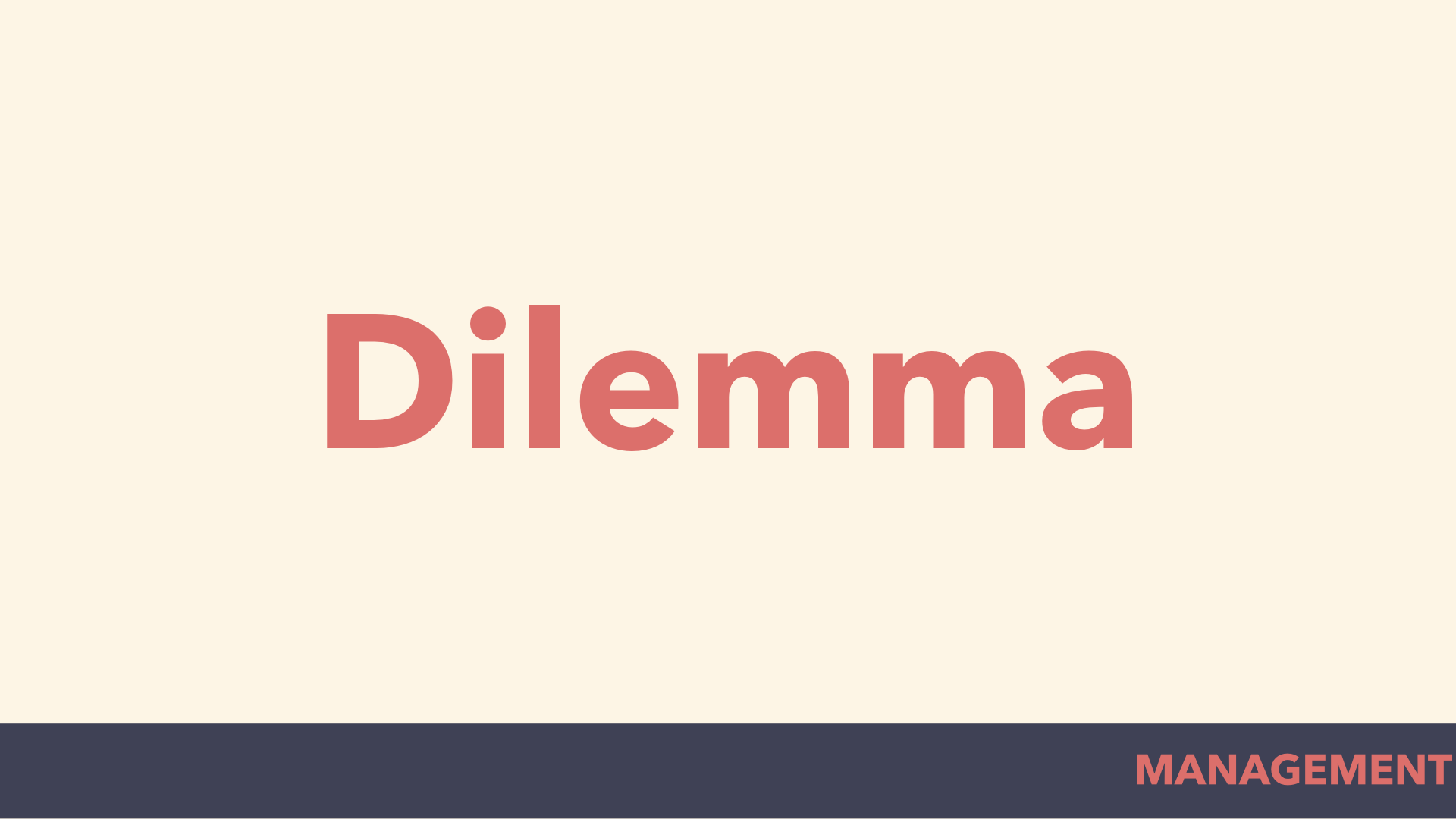
褒めないと自信がつかない?褒めると過信する?
褒めると自信がつかないし、受け取り方を間違われると過信してしまうし、どうしよう?となる現象を「マネジメントの褒めジレンマ」といいます。(今僕が決めました)
さて、ここまで読んでいただいて違和感を感じていないでしょうか?そもそも何のために褒めることが必要なのか?という点です。
結論から言うと、その人がもっている「自己認識と能力」のバランスを調整するために褒めます。が悪いメンバー、シンプルに言うと「能力があるのに自信がない人」は褒めた方がいいです。
褒める目的は、自分の能力を正確に認識させるために褒めます。なにが?どこまで?どれくらい?できるようになっているか?をハッキリ認識させ、できる事とできない事の線引を本人にさせる為です。
決して、気持ちよくさせたり、上司が嫌われない為に褒めるわけではありません。
褒めるマネジメントで自己認識をさせる効果

自分の能力を正しく認識するとどういった効果があるのでしょうか?シンプルに言うと、強みを発揮しやすくなり、弱みを補填しする方法を考えます。
シンプルに言ってるようで、ぜんぜんシンプルじゃないですね。
「今、なにができて次なにができるようになるか?失敗する時はどういうとこで、それを防ぐ為にはどうすればよいか?」を考えさせることができます。
それが、正しく自分の能力を認識させる効果です。
強みを伸ばし、弱みをカバーする方法を考えさせます。
褒めるマネジメントは全員に使うべきか?

結論から言うと、全員に使うか?という問いがそもそもズレています。褒めるマネジメントの目的は「自分の能力を正しく認識させる」ことでした。
その為、褒めるマネジメントの対象は、「自分の能力を正しく認識できていない人」になります。同じ人でも、仕事内容やタイミングによって、それができていないことがあります。それを修正する為に褒めます。
褒めるマネジメントではどれくらい褒めればいいのか?

褒めすぎると過信になり、逆効果になってしまいます。ではどれくらい褒めればいいのか?
メンバーが「自分の能力を正しく認識できるくらい」褒めます。つまり具体的にどういうことができる様になっているという、ポジティブなフィードバックをすればOKです。
漠然とした「すごいね!」「よくやった」「感謝している」という言葉だけでなく、「なにを」「なぜ」評価しているのか?を説明しないと正しい自己認識になりませんので、そもそも褒めたことになりません。
褒めるマネジメントで過信を防ぐ方法

過信という状態は「自分が考えている能力>実力」という状態です。できないのにできると思っていたり、少し褒めた事を拡大解釈して、すごくできると思い込んでしまったりという状況です。
これを防ぐのは、とても簡単です。期待しているハードルを上げればいいだけです。
「自分が考えている能力>実力<期待している能力」間の実績を抜くと、
「自分が考えている能力<期待している能力」という構図です。
それだと「調子に乗り続ける」と思うかもしれませんが、期待が高いので、次に褒められる事はありません。そうすると次のフィードバックでは次の構図に変わります。
「自分が考えている能力=実力=期待している能力」
あえて、高い課題を提示してできない事を自覚させればいいのです。そうして、それを繰り返していきましょう。
正しい自己認識の後に、期待することが成長させる

褒めて正しく自己認識をした後に、次に褒められる様になるためには、ここまでこないと褒めないよ。という提示をすることが、褒めるマネジメントではセットで必要です。
できたことを褒めるだけではなく、次はなにをできるようになってほしいのか?を提示しないと、褒めるマネジメントはただのご機嫌取りになってしまいます。
褒めるマネジメントのまとめ

いかがでしょうか?褒めるマネジメント!「マネジメントの褒めジレンマ」から抜け出せそうでしょうか?
少しでもこの記事がお役に立てば幸いです。
 初めてのマネジメントで考えること、マネジメントの定義を3分で解説【初級】
初めてのマネジメントで考えること、マネジメントの定義を3分で解説【初級】
 マネジメントの役割で最も重要なことは人材育成。考え方とポイントを3分でマスター【中級】
マネジメントの役割で最も重要なことは人材育成。考え方とポイントを3分でマスター【中級】
 Simple WORK
Simple WORK