本気でチームは変えられる!
と、麻野さんは思っている。僕は無理なチームもあると思う。THE TEAM LICENSE PROGRAM 研修に参加した時、どれだけ本気で、麻野さんが「すべてのチームは変えられる」と思っているかが伝わってきた。
実際にあらゆる企業に入り込み、変革してきた経験と、ご自身のチームでも変革したことが大きいな証拠である。
この記事の最後に、麻野さんがリーダーでもある、リンクアンドモチベーションの「モチベーションクラウド」の動画(ドキュメンタリー)もつけているので、そちらもぜひ見てほしい。
チーム変革のコンサルタント会社リンクアンドモチベーションの取締役麻野浩司氏の著書 「THE TEAM 5つの法則」
ここでは、第4章の意思決定の法則、第5章の共感創造の法則を考察していく。
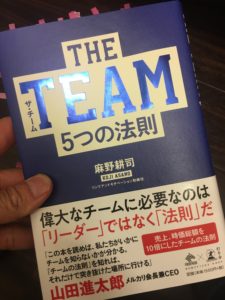 書評『THE TEAM 5つの法則』要約・レビュー (著者:麻野耕司) 第1章・第2章
書評『THE TEAM 5つの法則』要約・レビュー (著者:麻野耕司) 第1章・第2章
 書評『THE TEAM 5つの法則』要約・レビュー (著者:麻野耕司) 第3章
書評『THE TEAM 5つの法則』要約・レビュー (著者:麻野耕司) 第3章
 THE TEAM 5つの法則 著:麻野耕司 動画まとめ
THE TEAM 5つの法則 著:麻野耕司 動画まとめ
THE TEAM LICENSE PROGRAM研修関連記事はこちら↓
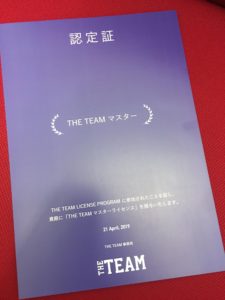 THE TEAM LICENSE PROGRAM 研修
THE TEAM LICENSE PROGRAM 研修
目次
第4章 Decision(意思決定)の法則[進むべき道を示せ]
理想的な意思決定とは?
独裁!最高?
チームでの意思決定の方法は、どの方法がよいのでしょうか?
3つの意思決定方法とそれぞれのメリット・デメリットがあります。
3つの意思決定方法は以下の3つ。
「独裁」VS「多数決」VS「合議」
THE TEAM 5つの法則 著:麻野耕司
独裁にはいいイメージがなく、話し合いできめるがの正しいとされているのが一般的です。
実際にはどの決め方がいいのかはチームによって異なります。
必ずしも独裁が間違っている訳ではないのです。
トップダウンの方が機能することも多く、全てにおいて民主主義が正しいわけではありません。
ただ、「多数決で決めなさい。」
と小さい頃から民主主義が正しい!と教育されてきています。
そのため、企業活動においても、その方法が正しいと勘違いをしてしまっています。
これは、国家にも言えることです。
実は独裁政権の方が社会がうまく回っているという地域や国は存在します。
宗教的な対立が過激な地域では、独裁の方が機能していたケースもあります。
独裁政権が崩れて、良かった!と思ったら、意見が違いすぎて、民主主義が成り立たない国や地域はいくつもあります。
どの勢力が多数になり、主権を握るかを決めるために、対立と内戦が起きてしまっています。
- 独裁は必ずしも悪いわけじゃない
意思決定に強弱がある?

「強い意思決定」と「速い意思決定」を意思決定者が心がけること
THE TEAM 5つの法則 著:麻野耕司
この第4章で、一番好きな言葉が上記の言葉です。
「強い意思決定」決まったこと、決めたことを実現し、正解にするために、全力をつくす。
「速い意思決定」をすることで、多少の間違いも修正できる時間が与えられる。
意思決定が遅いと修正が間に合わないケースも出てきます。
「高速でPDCAをまわす」ことは、ソフトバンクの孫さんも推奨しています。
孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきたすごいPDCA 感想まとめにソフトバンク流のPDCAについては詳しく書いてあります。
「ファーストチョイス理論」についても記載されています。
- ファーストチョイス理論とは・・・チェスで「5秒で決めた手」と「30分考えた手」は、80%が同じなっている
8割同じなら、29分95秒速い意思決定をして、すぐに動き出した方がいいです。
もし、その意思決定が間違っていたとしても、それに気づいて修正するまでの猶予が29分95秒もあります。
30分かけて考えていては、時間がもったいないです。
最悪なのは、決断しないことです。
判断ができないから先延ばしにする。チームを運営する上で、絶対にやってはいけないことです。
とにかく決めて動きはじめないといけないです。
- 速く、強い意思決定をしよう!
本書とは関係ありませんが、仕事が納期から遅れてしまう原因のほとんどは、指示を受けてからすぐに着手すると決めていないことが原因です。
組織の意思決定ではないですが、個人の意思決定が遅いことで仕事の納期が遅れることがあります。
例えば、上司から2週間後に、なにかの調査した結果を報告するように指示をうけたとします。
多くの人は指示を受けた日には何もしないで、いつから始めるかを考えます。
そして、期日内に終わらせることができると思うタイミングで着手します。
でも、実際に作業をしてみると、想像していたより時間がかかる事に気づきます。
想像よりも多くの工数が必要だったり、上司に確認しないといけないことが出てきたりします。
期日がすでに近づいているのに、上司に相談に行きます。
なんでまだそんなところなの?
期日までにできるの?
と言われて、がんばります!とやってみたけど、
結局、期日を守れない・・・・
上司に怒られる経験をしたことがある人もいると思います。
原因はすぐに着手すると決めていないことです。
指示されたら、とりあえず、すぐに着手してみる。
想像していたことと違うことがないか、上司からの指示で不足がないか、イレギュラーはどんなことが想定されるのか?
すこし着手してみて、どれくらいの日数で終わるのか?を考えます。
そして、「上司が決めた期日」ではなく、「自分が決めた期日」を上司が決めた期日の前日か2日前くらいに設定しまう。
「自分が決めた期日」を目指してスケジュールで動けば、ほとんどの仕事で期日を守れます。
メンバーに納得感がある意思決定を最短で、できるチームは最強です。
納得感があれば、特に目標設定については納得感が自主性と新たな発想を生むことができます。
意思決定の過程を可視化しておけば、納得感もあるし、次のリーダーとなる人材が育つのも早くなります。
「独裁」という言葉をあえて使っている理由はおそらく
「独裁」>「トップダウン」
「独裁」は「トップダウン」よりも上位概念である。
チームの状況を「独裁」と捉えてしまっている人に適応されにくい法則になるからでしょう。
どの方法で意思決定をしても、間違える時はあります。
結局、その意思決定が正解か、不正解かの判断を速くして、修正が必要ならばすぐに修正していくことが必要です。
そのためには、決定されたことに対する強い行動力が必要なんです。
私の考えとしては、会社における意思決定は常にリーダーが独断でやるでいいと思っています。
多数決や合議ではなく、正しい情報をリーダーに提供する役割をメンバーが出来ていれば、判断を間違えることは少なくなります。
第5章 Engagement(共感創造)の法則[力を出しきれ]
やっぱり人は「感情」で動く
感情
役職の高い人は、モチベーションは関係ないと思っている人もいます。
でも、実際のところモチベーションがまったく関係ないことはありえません。
「些細なことでモチベーションを下げないようにする」ことと「モチベーションの存在を認めないこと」は別のこと
THE TEAM 5つの法則 著:麻野耕司
役職の高い人は、モチベーションに対して、マイナスの影響を受けることが極端に少なくなっているだけです。
役職が高くない人は、どうすればモチベーションに対する、マイナスの影響を受けなくなるのでしょうか?
そのためには、考え方を「個人」から「役割」に変える必要があります。
会社は「役割」に給料が支払らっています。
人材である「個人」に給料が支払われている訳ではないのです。
「個人」の状態に関係なく、「役割」に給料が支払われていると考えないといけません。
会社から求められている「役割」を果たすことが、「個人」が会社に所属している存在意義なので、「役割」を果たすことに集中しましょう。
役職が高い人は「役割」を果たすことに集中しています。「役割」を果たすためには、「個人」のモチベーションが高く保つ必要があります。
モチベーションが下がるようなことがあっても、「役割」を果たすためには、モチベーションを下げている場合ではないので、下げないようにしましょう。
メンバーマネジメントに関するヒントはこちらもどうぞ↓
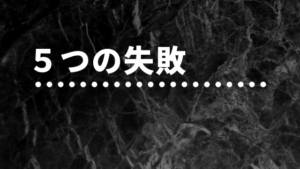 マネジメント能力を上げる5つのポイント!これだけできれば、マネジメントの質が上がる!
マネジメント能力を上げる5つのポイント!これだけできれば、マネジメントの質が上がる!
 初めてのマネジメントで考えること、マネジメントの定義を3分で解説【初級】
初めてのマネジメントで考えること、マネジメントの定義を3分で解説【初級】
チームとメンバーの結びつき(エンゲージメント)を高める4P
エンゲージメント
「エンゲージメント」という言葉は聞き慣れないですが、ここでは、「チームに貢献しようとするモチベーション」を表す言葉です。
その「エンゲージメント」を高めるための4つのポイントがコレです。
- Philosophy(理念・方針)
- Profession(活動・成長)
- People(人材・風土)
- Privilege(待遇・特権)
チームのメンバーに、次の質問をした時に同じ回答が返ってくれば、いいチームです。
- チームとして、この4つのどれを一番大切にするのか?
- なぜそれを大切にするのか?
そこで重要になるのが、採用です。
会社のどこに魅力を感じているのか?自分の価値をどこで発揮しようとするのか?をきちんと見極めて採用しないといけなません。
第5章の例として、「ディズニー」「マッキンゼー」「リクルート」があげられています。
この3社で働いている社員が大切にしてるものは違うイメージです。それぞれの社内では、同じような価値観の人が働いているイメージもわきます。
この3社のようにイメージできる状態に「自分のチームもなる」ために活用するのが4つのPです。
エンゲージメントを生み出す方法
エンゲージメントを生み出す方程式
エンゲージメント=報酬・目標の魅力(やりたい)×達成可能性(やれる)×危機感(やるべき)
THE TEAM 5つの法則 著:麻野耕司
「達成可能性(やれる)」がわかりにくいかもしれないです。
段階的に成長してできることを増やしていくことです。最終的な目標に届くまでの中間目標のイメージで使われている表現です。
3社の違いがわかりやすく解説され、エンゲージメントがどのように作用しているかイメージできるようになります。
褒める事を推奨されていますが、失敗することもありますので、褒めるマネジメントが失敗する原因と対策を参考にしてみてください。
モチベーションがゼロで働いている人はいないです。
モチベーションの高い、低いはあるかもしれないですが、どんなに低くても必ずあります。
モチベーションがゼロだと働かないからです。
チームへの貢献をする意欲(エンゲージメント)が強い組織は、まとまりがあり強いです。
個人が求める報酬がなにで、どのように達成していくのか?達成できないとどうなるのか?
明確な目標と、適正な危機感が共存している組織がエンゲージメントが高い組織です。
特別収録 チームの落とし穴
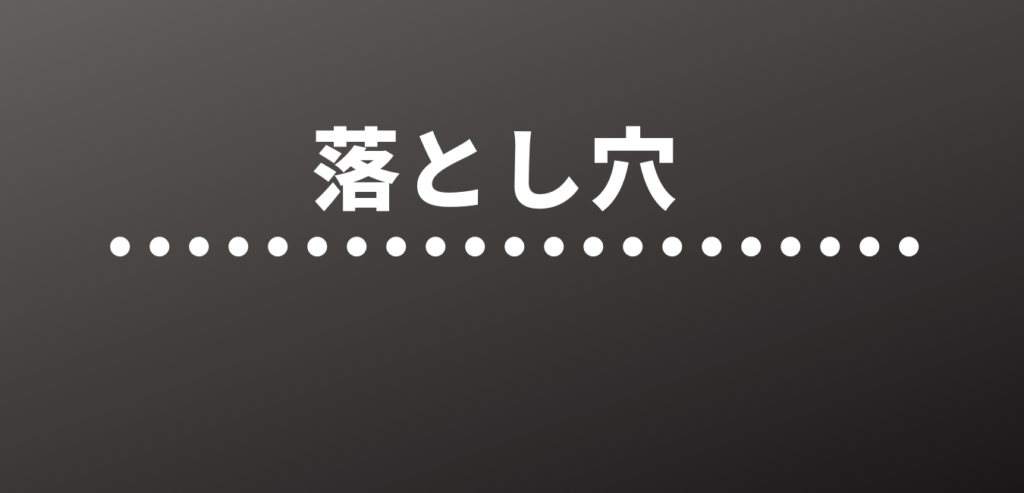
読者の反響が一番大きかったのが、この「チームの落とし穴」だと著者が語っていました。
それだけ、チーム運営の難しさがこの部分に表現されていると言えます。
個人で活動している時には絶対に起こらないことが、チームではおこります。
それは集団心理が働いてしまうからです。本書で紹介されている集団心理は4つ。
- 同調バイアス
- 社会的権威
- 社会的手抜き
- 参照点バイアス
同調バイアスや社会的権威は、責任の回避からくる。チームになると責任の所在が曖昧にすることができる。
同調バイアスはだれかが言った意見に便乗すること。本当はちょっと違うと思っていても多数の意見に流れておくことを言います。
社会的権威は、「偉い人の意見は正しい!」と思い込んでしまうことです。
社会的手抜きは、一人ぐらいサボってもばれないよね。と思うことです。
社会的手抜きについては3分でわかる!チームワークの良い職場の作り方・社会的手抜きの原因と対策【モチベーション】で原因と対策について書いています。
参照点バイアスは、リーダーも期日遅れるから、自分も遅れていいと思ってしまう心理です。
これらの集団心理が発生するかしないかは、単に人数規模が問題なのではありません。
メンバーの関係性も影響します。これらの落とし穴を防ぐ方法は唯一つ!
最終章 私たちの運命を変えた 「チームの法則」
麻野さんのチームがどうやってチームとして機能するようにしてきたのか?なっ結果を出せたのか、このムービーの物語をみてください。
5つの法則を使って、具体的に著者が経験した原体験です。
組織論の中でも、抽象度が高い、モチベーションを科学されてきた方がわかりやすく体系的に説明をしてくれています。
なにより著者自身が実行し、効果が実証されているのがすごいです。
人の能力を発揮し、それにレバレッジをかけるのがチーム。
チームをつくれば、人の能力は自然と発揮され、結果もついてきます。
「チームの落とし穴」に記載のある「集団心理」については、意図的に全員が指摘し合うようなことができないと、成果が小さくなってしまいます。
組織が大きくなればなるほど、失敗の確率も比例してあがります。
それを防ぐには全員が、チームを良くするぞ!とこの5つの法則を理解し、使っていくことが必要だと気付かされました。
ちょっと疲れたので、漫画でも読もうかなと思った方にオススメをまとめました。↓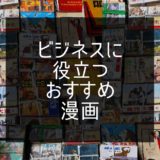 ビジネスに役立つおすすめ漫画9選
ビジネスに役立つおすすめ漫画9選
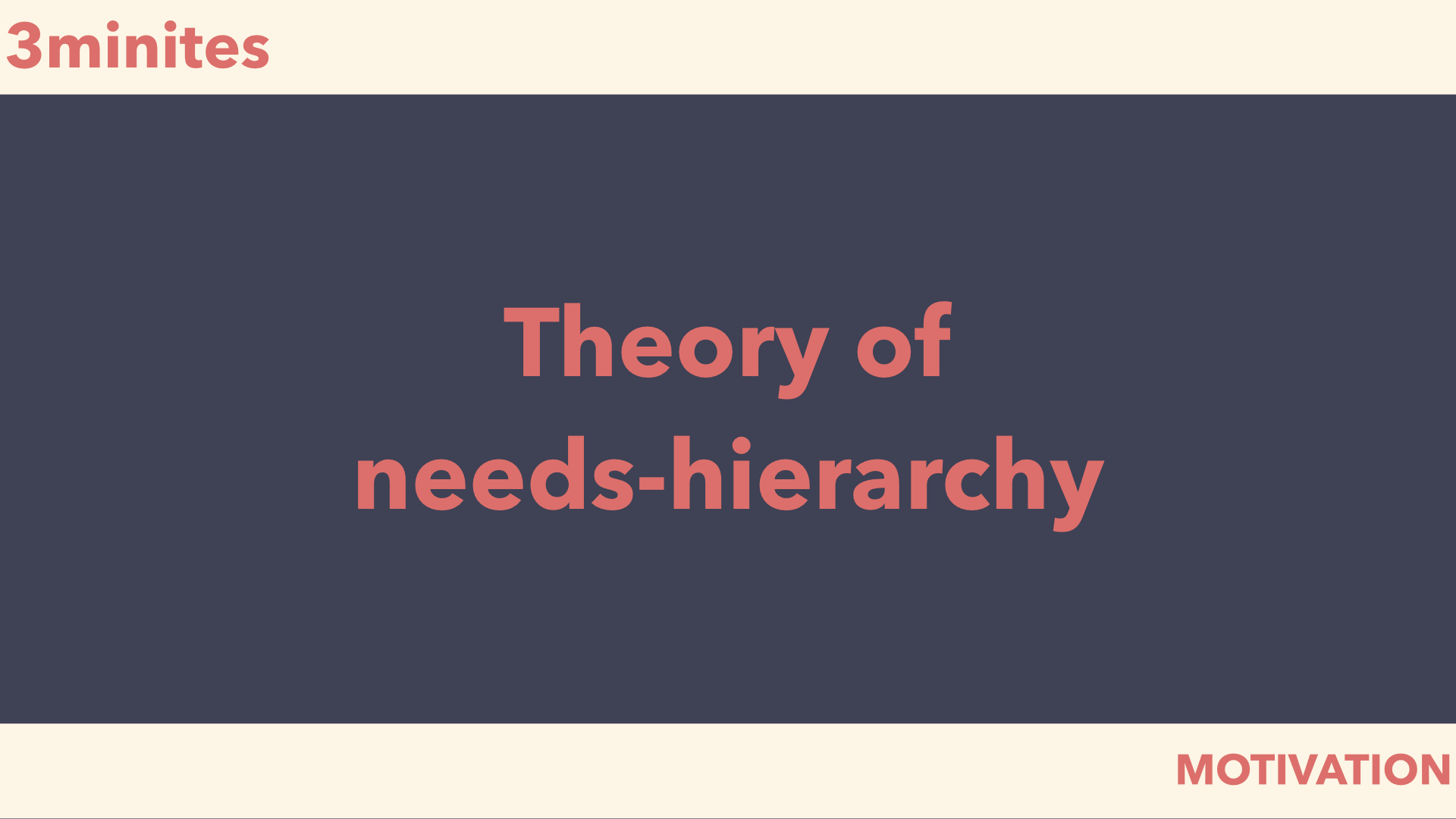 モチベーション理論|マズローの欲求段階説をマネジメントで活用する方法
モチベーション理論|マズローの欲求段階説をマネジメントで活用する方法
 才能の見つけ方!徹底的な自己分析で、自分の強み・隠れた才能を見つけよう!
才能の見つけ方!徹底的な自己分析で、自分の強み・隠れた才能を見つけよう!
 モチベーションを高く保つ方法と積極性を失わない考え方
モチベーションを高く保つ方法と積極性を失わない考え方
 Simple WORK
Simple WORK 






