会社のIR情報を見て、企業分析をしている。という人も営業職の中にはいると思います。それに転職する時は、IR情報が開示されていれば、絶対にみた方がいいです。
その為には決算書類を見れるようになる必要があります。でも、なかなか勉強する時間が取れない。別に資格を取るつもりはないし、「今、困っていない」から勉強しなくていいや。と思っている人もいるかも知れません。
昇進し、昇格して上層部になればなるほど、財務会計の知識がある人とない人では、戦略のレベルが違ったり、知らない間に不正してしまったり、企業間の取引で融通をきかせることができなかったりということが起こってしまいます。
売上のだけの責任ではなく、経費の責任まで持てるようになると、一気にレベルが上がります。経費コントロールには財務会計の基礎知識が重要になります。そのポジションになってから学ぶでは、結果を出すタイミングが遅れてしまいます。
ここでは、財務会計の基本である、「財務会計」と「管理会計」の違い、「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の概要を説明していきます。
苦手な人もいるかもしれませんが、難しく考える必要はありません。企業のお小遣い帳くらいのイメージでいいと思います。
一段高い目線を持つ為に、学んでいきましょう。
目次
そもそも財務会計とは?
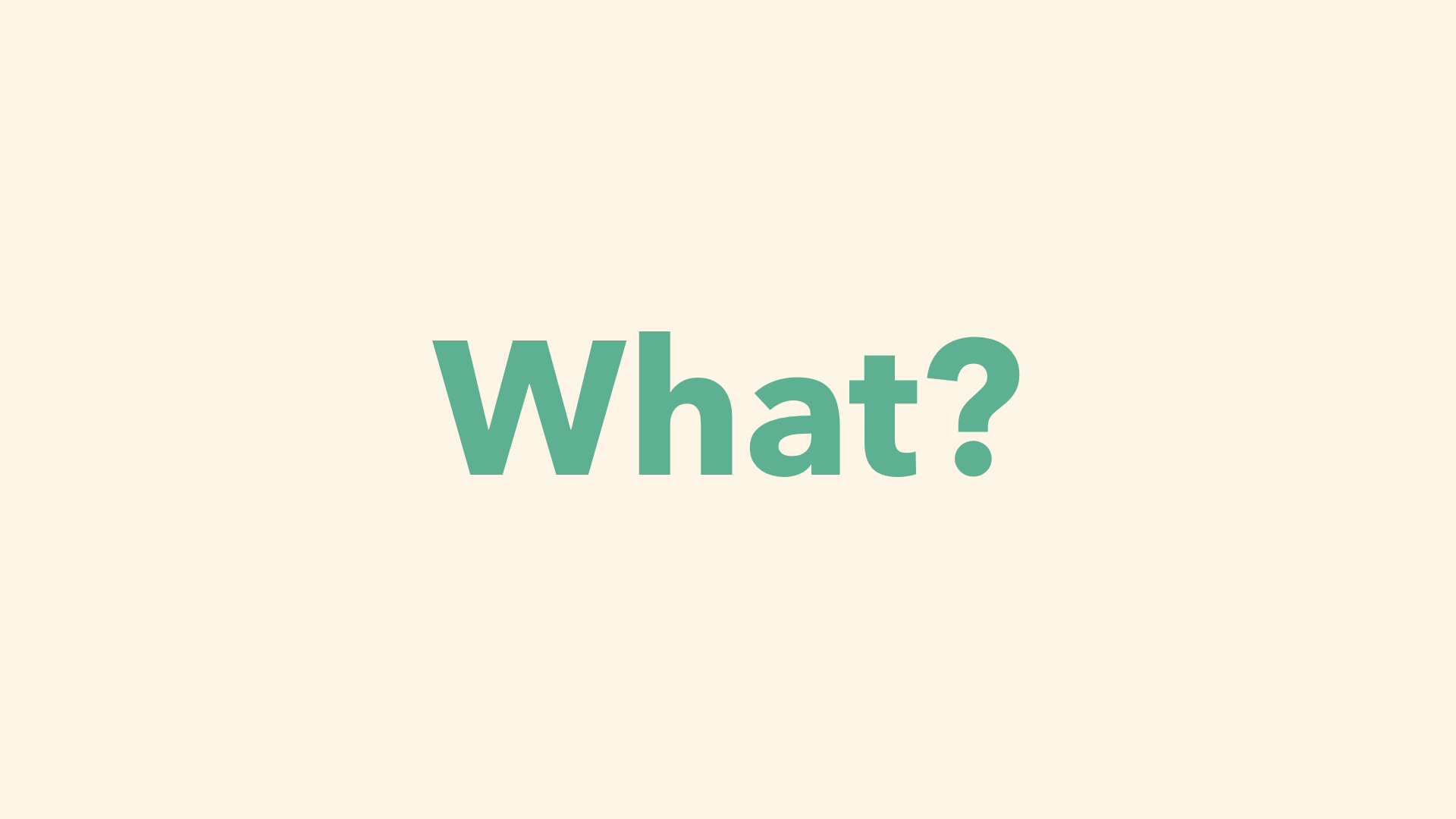
財務=ファイナンス
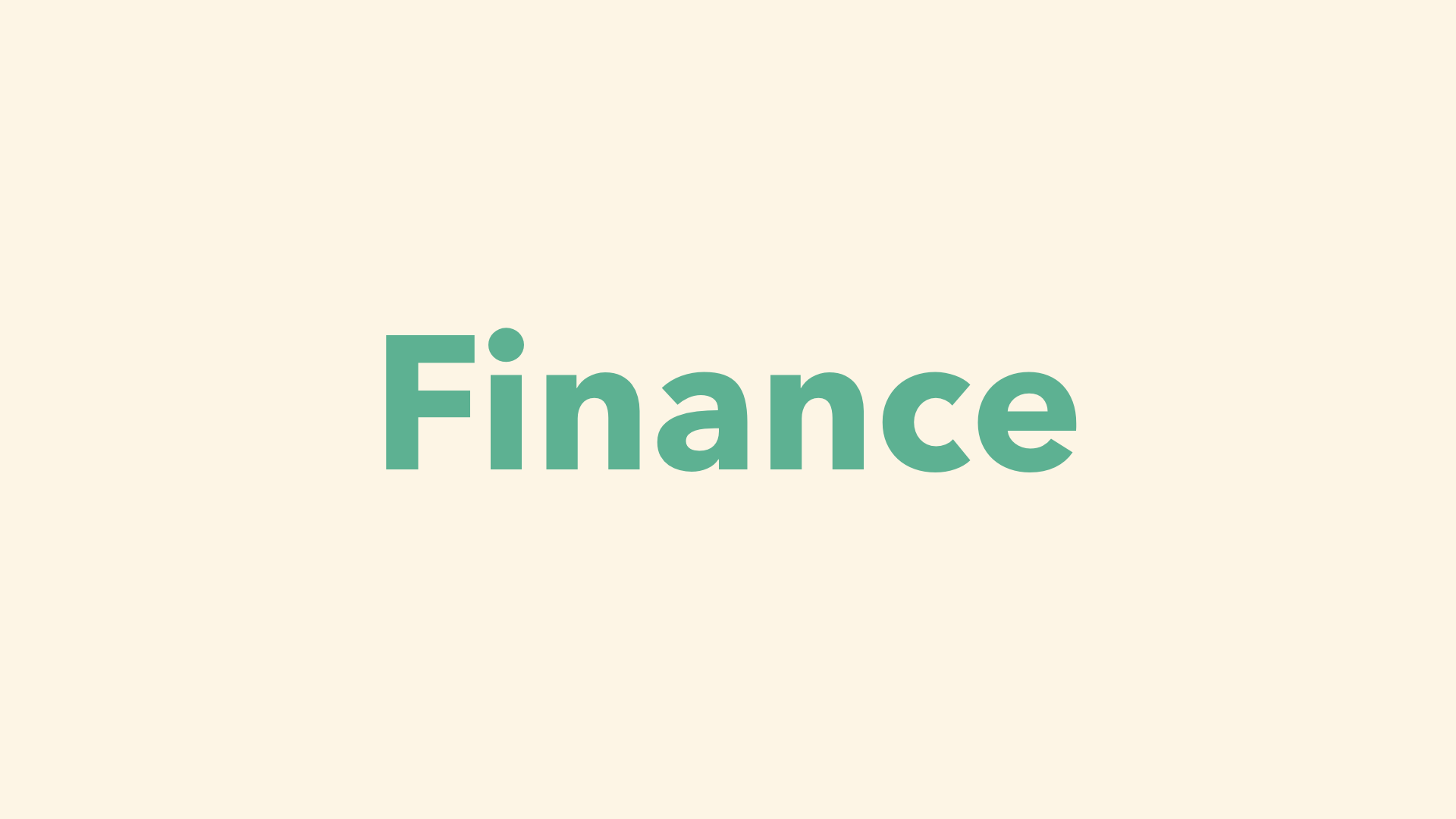
財務・会計と一言で表現していますが、財務はファイナンス、会計はアカウンティングと英語では別れます。
ファイナンスは、日本語では、財務、財政、金融などと訳されます。ファイナンスは資金の”流れ”に関する活動を広く意味します。
ファイナンスという言葉の意味は広く、国家や個人に関してもファイナンスという言葉を使いますが、ここでは企業を主体とする「コーポレート・ファイナンス(企業財務)」のことを指しています。
企業価値を最大化することがファイナンスの目的です。どこにお金を使うのが、効果的なのかを決めることが必要です。投資の意思決定、資金調達の意思決定、利益分配の意思決定に関わる部分をファイナンスと考えましょう。
会計=アカウンティング
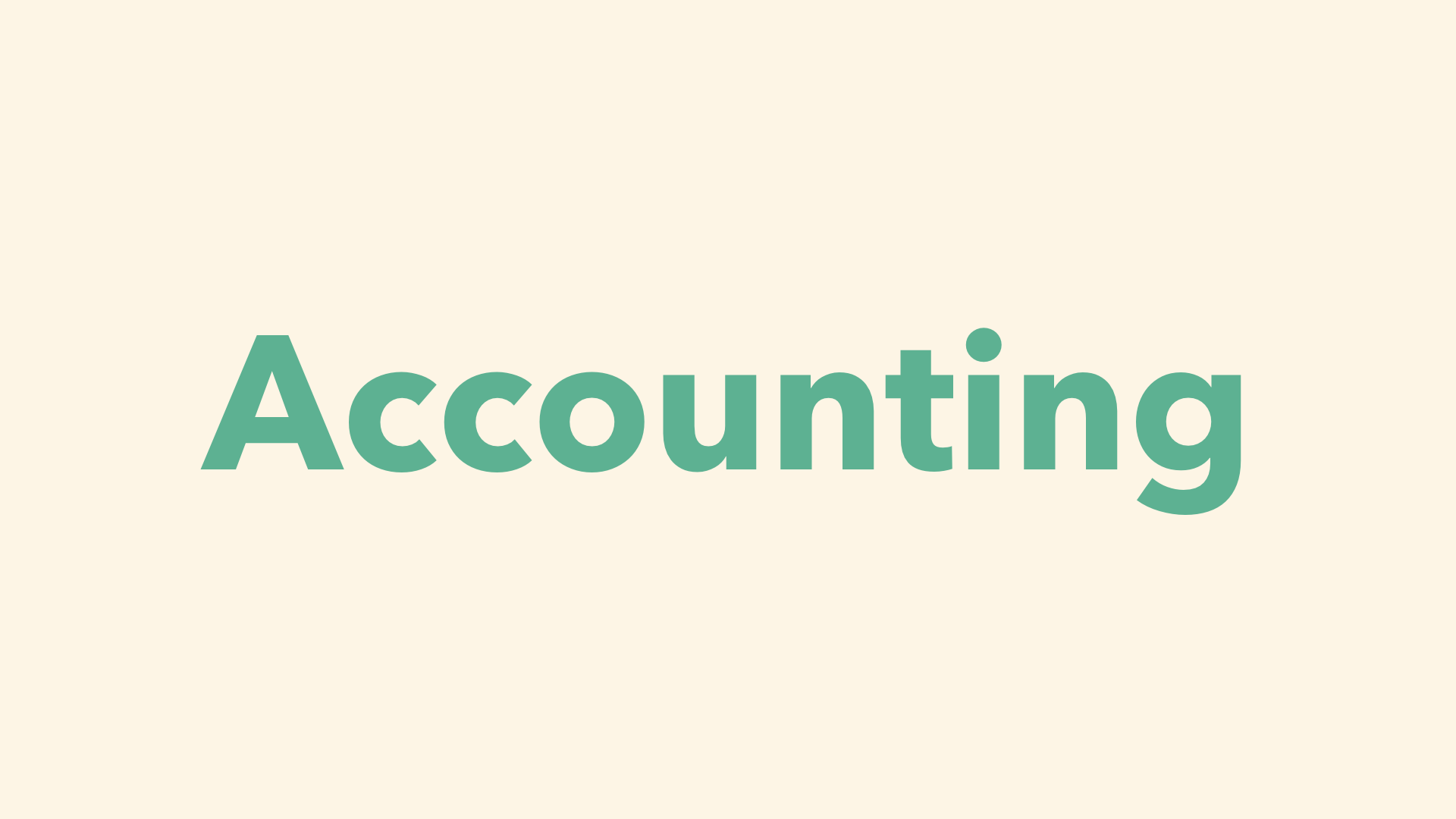
アカウンティング・会計は企業の財政状態や利益を計算する為の方法のことです。会計が必要な理由は単純です。
「会社の状態」を同じ条件で比較的できる表を投資家に開示して、「資金を調達」することが目的です。会社が儲かっているのか?儲かっていないのか?どれくらい投資しているのか?未来も儲かるのか?というようなことを開示してい、投資家から資金を集めることが目的です。
会社の通信簿がアカウンティングと考えましょう
会計には2種類ある 財務会計と管理会計の違い
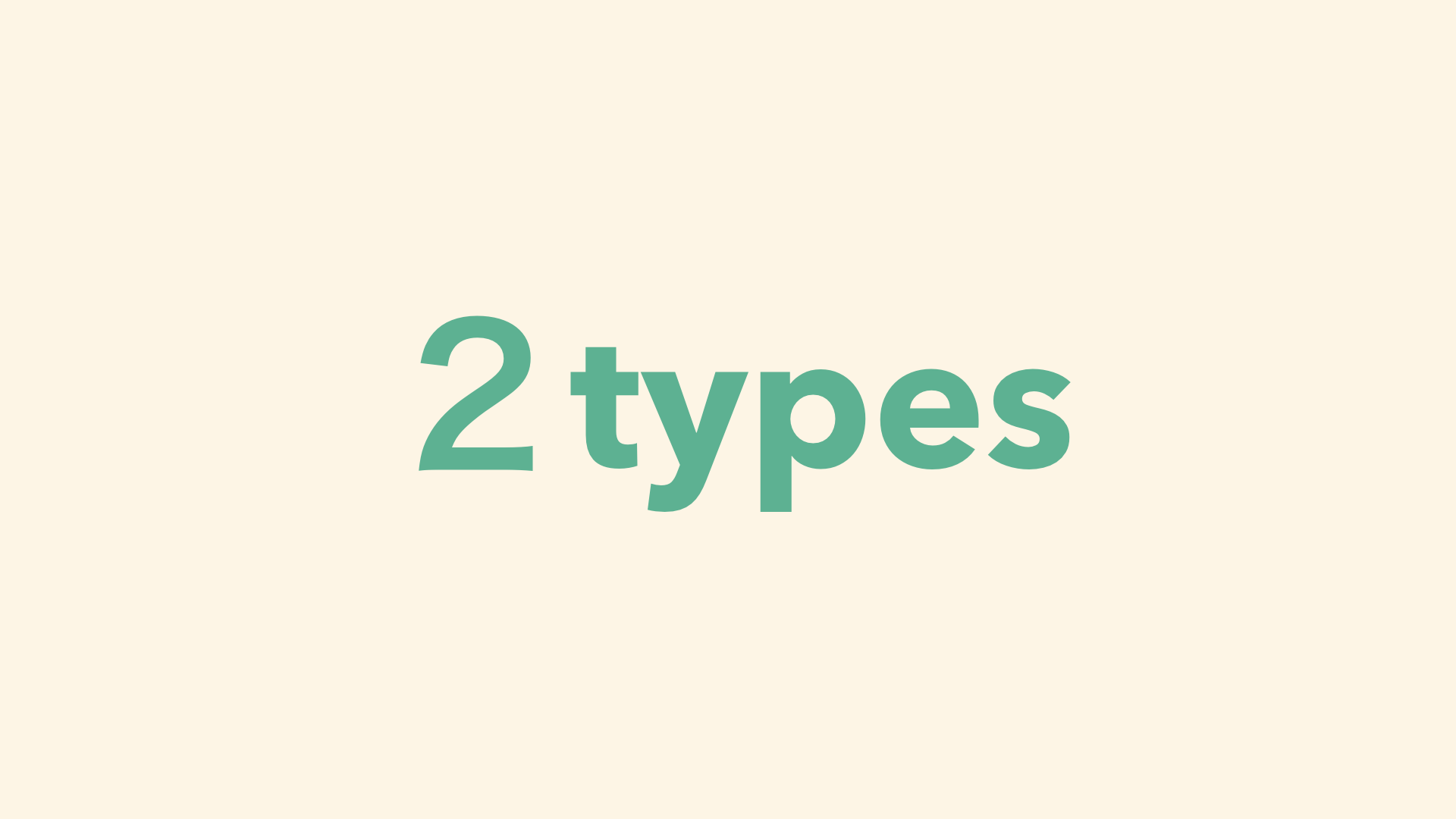
会計はアカウンティングであり、会社の通信簿なのですが、通信簿の基準は学校によってバラバラです。5段階評価のところもあれば、10段階評価のところもあります。5段階評価の”3”と10段階評価の”5”、”6”、”7”ではどちらが良いのかがわからないです。
基準がバラバラなので、比較できません。通信簿やお小遣い帳の基準が会計であり、その書き方のルールを決めているのが”簿記”です。
投資家から資金を集める為に「同じ条件」で比較できる表を作っていくことが必要なのですが、投資家向けの表を「財務会計」といいます。投資家にどういった状態かをわかりやすくする為です。
もう一つ、「管理会計」と言われるものがあります。これは社内で管理する物であり、投資家に開示している「財務会計」とは基準や項目の細かさなどが違います。
投資を募る為の、外部に向けた「財務会計」と内部の経営管理や詳細な意思決定に必要な「管理会計」となります。
とはいえ、どちらの報告にも「財務諸表」が持ちられます。財務諸表とは、「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の3つで、これを「財務3表」ということもあります。
「財務会計」はこの3つをマストで作成しなければいけませんが、「管理会計」は社内のことですので、「損益計算書」までは各部門ごとに把握していて、「貸借対照表」「キャッシュフロー計算書」は全社で管理という企業も多いと思います。
貸借対照表の資産を部門ごとに分けるのが難しいからです。
損益計算書とは? PL概要
一定期間における企業の経営成績を明らかにする為の財務諸表です。一定期間というのは、通常は1事業年度となります。3月決算の会社であれば、4月1日から翌年の3月末日までの期間の結果を表しています。
損益計算書はProfit and Loss Statementなので、P/Lと言われています。利益と損失を表現しているということになります。
ここではどういった情報が記載され、なにがわかる表なのか?簡単に説明します。
損益計算書の構造
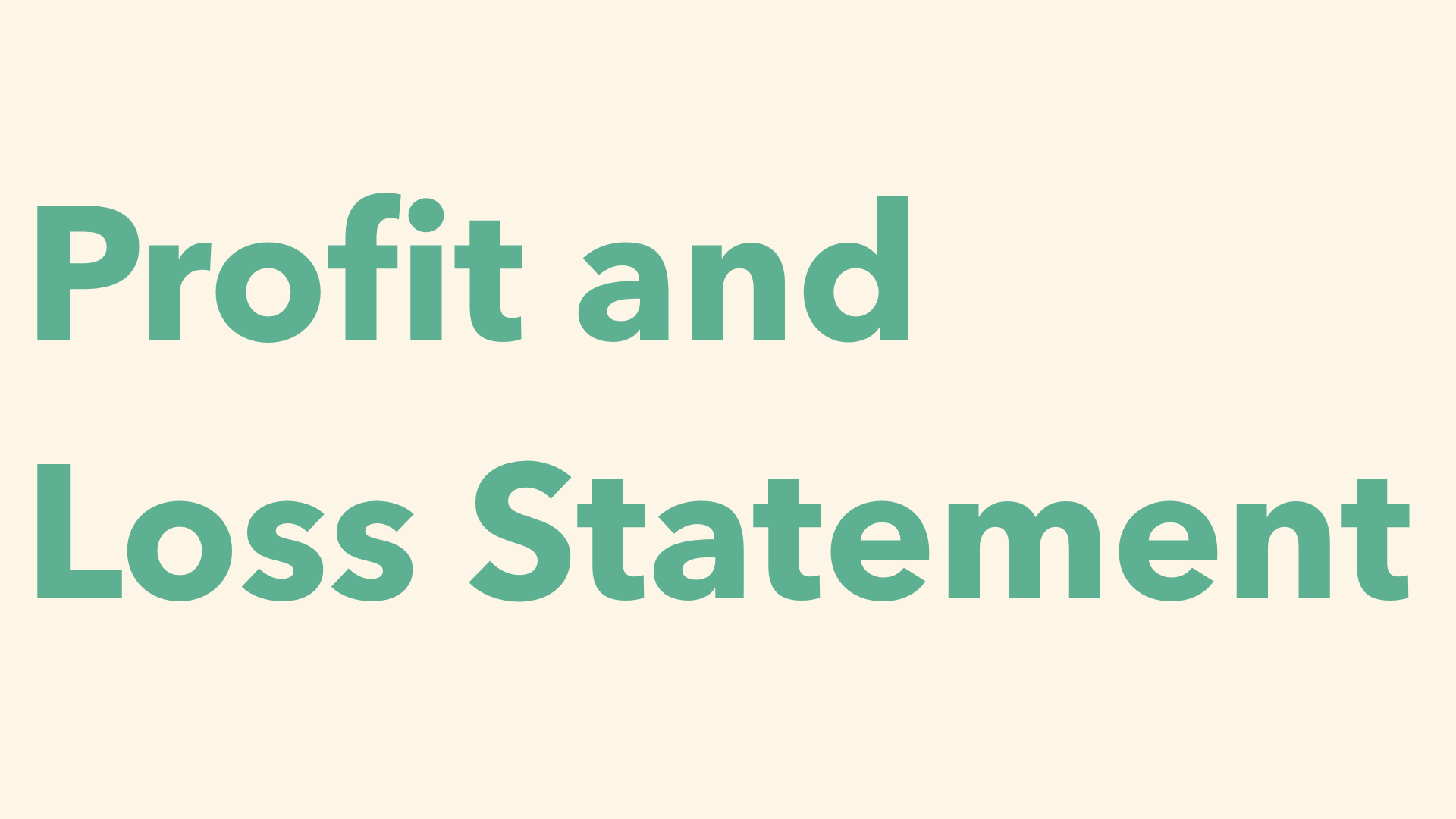
(原価なので、人の経費などはここでは含めない)
(ここでは営業以外の経理や、人事などの経費も含める)
営業以外の収益(預金や貸付金の利息や他社株式の配当金)と費用(借入金の利息)を計算し、プラスの場合は、営業利益に加算。マイナスの場合は営業利益から差し引く
特別利益(固定資産の売却で得た利益)特別損失(固定資産を売却して損をした損失・災害で損失が発生した場合)
- 営業利益=本業で稼ぐチカラを表す
- 経常利益=本業以外の資産運用状況も含めたチカラを表す
- 税引前当期純利益=特別な状況がもたらすインパクトを表す
- 当期純利益=最終的に会社が来期以降に使える資金を表す
シンプルに説明すると上記のようになります。自社の営業利益がいくらで、自分の事業部や領域がいくらくらいのインパクトを与えているのか?を把握していることは大切です。
経常利益から下の数字は、経営層や経理部門の資金的な戦略がうまく行っているのかうまく行っていないのかを表しているといえます。
新聞やニュースで、何億円の利益!や、何億円の損失!と報道されている時にも、営業利益か、経常利益か、税引前当期純利益か、当期純利益かによって意味合いが違います。
見出しの大きな数字に踊らされることなく、その数字がなにを表しているのか?一時的な影響なのか?継続的なものなのか?を考える必要があります。
それは自社の数字でも同じです、大きな会社では他の事業部の状況がわからず、IRでしか、全社の情報がわからないという会社も少なくないと思います。他の事業部や、全社の状況を理解し、自分の所属する事業部の位置付けや期待されている役割や今後取るべき戦略を選定していかなければいけません。
会社の状況がわかっていないと判断を間違い、大きな損失を会社にもたらしてしまうかもしれません。自分の所属する事業部だけが利益をだしていて、他の事業部が赤字だらけ。本来は利益をある程度、残して借入金の返済に当てたりしなければいけないのに、長期的な結果を求めた広告に投資をしてしまったりすることもありえてしまいます。
大きな責任と判断を任される前に、シュミレーションをする意味でも、損益計算書はマストで理解が必要と言える財務諸表の一つです。
特に、転職する時は営業利益と経常利益までは数年分見ておきたいです。
キャッシュフロー計算書とは? 概要
キャッシュは現金及び現金同等物の増減を表しています。違う表現をすると現金をどれくらい持っているのか?を表したものといえます。
例えば、今日1,000万の商品をお客様に販売したとします。その場で現金で取引をする企業は少なく、今月分の取引を全てまとめて、今月分として請求書を発行します。その請求書の金額を来月末に支払ってもらうという取引が一般的です。
売上は今月に上がっていますが、実際にお金が手元に入るのは来月の末になります。このタイムラグがあるので、損益計算書で出せている利益が必ずしも現金として手元にあるわけではありません。
手元にある現金や現金同等物をあらわした表がキャッシュフロー計算書です。
現金同等物というのは、3ヶ月以内に確実に現金化できる資産のことです。
キャッシュフロー計算書の構造
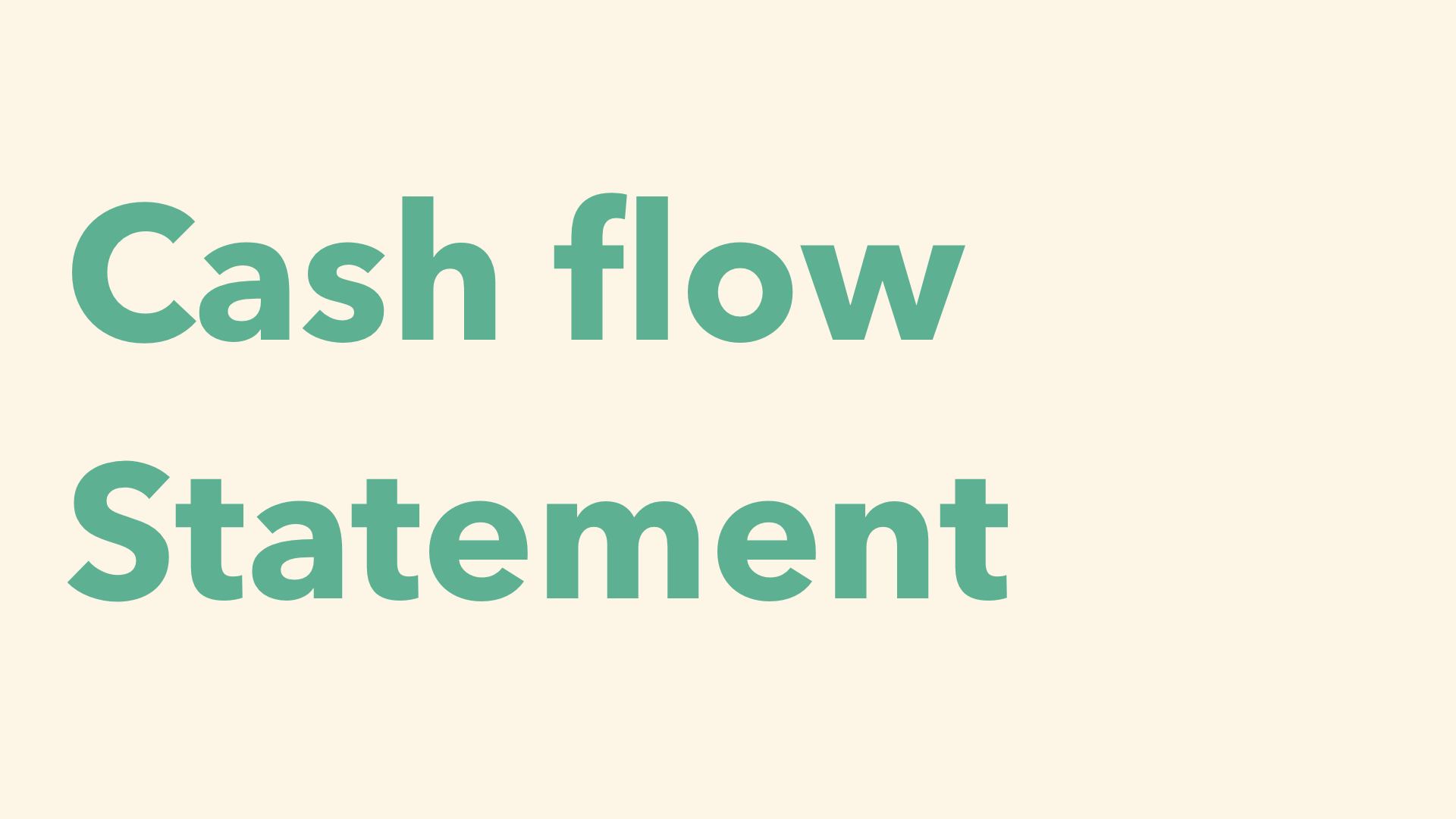
キャッシュフロー計算書は3つの区分されています。営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフローです。
営業・投資・財務それぞれの活動でのキャッシュの増減を表現しています。
- 営業活動によるキャッシュフロー:
企業が本業で稼いだキャッシュの増減
- 投資活動によるキャッシュフロー:
固定資産の取得や売却などの投資活動に使った、または投資活動で稼いだキャッシュのこと
- 財務活動によるキャッシュフロー:
資金の借り入れや返済、株主からの資金調達や配当の支払いなどによるキャッシュのこと
どんなに利益を出して儲かっているいわゆる黒字の会社でも、利益が現金になる時期が、現金が必要な時期よりも遅ければ、意味がなく、倒産してしまう。これを「黒字倒産」といいます。黒字かどうかは貸借対照表や損益計算書でわかりますが、現金があるかないか?はわからないです。
それをわかるようにしたのが、キャッシュフロー計算書です。1億の売掛金があり、来月末に入金される予定でも、今月末に100万円の返済ができなければ、倒産してしまいます。
黒字倒産が起こらない為にも、キャッシュがあることを把握するのに必要になった帳票です。
貸借対照表とは? BS概要
貸借対照表とは、ある時点(通常は事業年度末)における、企業の財務状態を表す帳票です。3月決算の会社は3月末時点での会社の状態を表しています。
損益計算書は1年分の成績だけなのですが、貸借対照表は創業してから、決算期までの累計の成績表と言えます。
一般的にBalance Sheet B/Sといわれます。名前の通り、資産と負債のバランスを表現している表です。
貸借対照表の構造

構造は非常にシンプルです。
なにに使っているのか?を表しているのが、資産の部(表の左側)
使っているお金はどこから出しているのか?を表現しているのが、負債の部と純資産の部(表の右側)
左側の資産は、右側に記載される負債と純資産(どの程度の負債(借り入れ)と純資産(株主資本))で成り立っているのかを表現しています。
資産と負債には流動と固定があり、流動の定義は1年以内に決済されるもの。固定は決済が1年以上に決済されるものとなります。
貸借対照表を見れば、なににお金を使っているのか?がわかります。前年度や競合他社と見比べるとその企業ごとの戦略がわかります。
資金の調達が借り入れからなのか、株主からなのか?利益からなのか?その資金をなにに投資しているのか?などの情報が読み取れるようになります。
■資産(左側に含まれる)の主な項目
- 現金及び預金
- 受取手形
- 売掛金
- 貸倒引当金
- 有価証券
- 商品
- 短期貸付金
- 建物
- 車両運搬具
- 土地
- 建設仮勘定
- 投資有価証券
- 長期貸付金
■負債(右側に含まれる)の主な項目
- 支払手形
- 買掛金
- 短期借入金
- 社債
- 長期借入金
■純資産(右側に含まれる)の主な項目
- 資本金
- 資本余剰金
- 資本準備金
- その他資本剰余金
- 利益余剰金
- 利益準備金
- その他利益余剰金
- 自己株式
これら項目が全てではありませんが、こういった項目があり、左右に別れて記載されていて、なににどれだけお金を使い、どうやってそのお金を調達しているのか?がわかる表です。
まとめ

 Simple WORK
Simple WORK 




