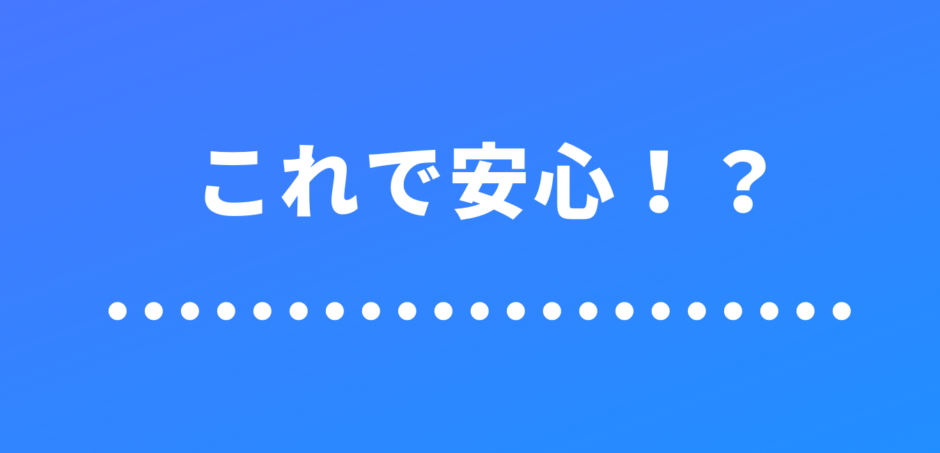会議で上司からの質問に答えられなくて、怒られた経験はありませんか?
僕はあります。特に悪い報告をする時に、その原因を把握できていなくて、怒られてましたね。原因がわからないので、対策もなく・・・今思えば浅かったと思います。
それからいろいろ勉強して、データ分析やロジカルシンキングの基本は理解しているつもりです。それをお伝えすることで、怒られる人が減ってほしいです。給料上がる人が増えるといいなと思って書くことにしました。
コンビニの店長とSVをしていた時は、徹底的にデータを分析していました。お店の売上が上がった原因。下がった原因を把握して対策を打たないといけないからです。
原因がこれかもしれないと仮説を立てて、確認して原因が仮説通りかどうかを確かめる。もし、仮説と違えばなにが違っていたのか?その原因に対策を立てて、結果をまたデータ分析。この繰り返しです。
そんなことばっかりしていました。そんな経験もあり、コンビニ以降の仕事ではデータを扱う仕事が多かったです。直近の人材会社でもデータ分析をして対策を立案したり、売上予測したり、KPI設計したり、業務設計したりしていました。
ほとんどのビジネスは結局「PDCA」をどれだけ早くたくさん回せるかで成功確率が変わってくると思います。
わかりやすい小売の例で「売上の原因分析の考え方」を解説していきます。ほとんどの業界で同じ構造なので、自分の業界に置き換えて考えてみてください。
上司に怒られる人がすこしでも減りますように。
目次
分解していくと答えが見えてくる
「売上」の分析〜 客数と客単価
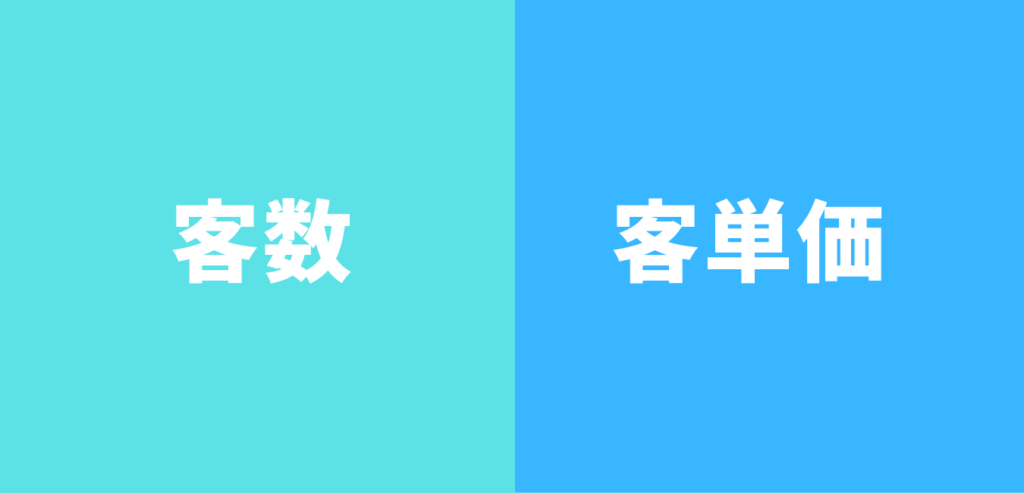
売上が上がったり、下がったりする原因を分析していくのですが、売上を構成するのはなにか?です。
お客様が商品を買った時に「チャリーン♫」と売上が上がります。
お客様が商品を買うことで上がるんです。だから、売上に影響を与えるのは「お客様」と「商品価格」です。
一人のお客様が買う商品は1つとは限りませんし、3つ買う時もあります。
Aさんがコーヒー1本120円とパン120円と新聞160円を買ったとすると売上は120+120+160=400円になります。
一人ひとりのお客様の”買い物”の積み重ねを1日や1ヶ月集計して、1日の売上とか1ヶ月の売上が判明します。一つの公式が成り立ちます。
客数が800人で、客単価が700円のお店の売上は560,000円になります。
売上に影響を与えるのは、客数と客単価の2つです。その2つしか原因がありません。いやいや他にも原因はあるよ!という人もいるかもしれませんが、その原因は「客数」「客単価」のどちらかに必ず影響を与えているのです。
売上を直接的に構成しているのは「客数」と「客単価」です。
これに購入頻度を入れる人もいますが、この公式の客数は”のべ客数”なので、1人のお客様が2回買い物したらそれは2人とカウントします。詳細は次の「客数」分析で説明します。
なぜ客数が増減したのか?
「客数」分析 新規と既存

次に「客数」を分解してみましょう。どんなお店でも2種類のお客様しか絶対に来店しません。それは、「初めてのお客様」か「リピーター」かのどちらかしかいません。
それ以外のお客様は存在しないです。
初めて買い物をしてくれた新しいお客様が「新規顧客」
リピートで何度も買い物にきてくれているお客様が「既存顧客」
現金決済ではお客様が「新規顧客」か「既存顧客」かわからないです。ベテランの従業員さんがあの人は初めてだと思っていても、その人が接客したことがないだけで、他の時間帯の常連さんだったなんてことはよくある話です。
今はキャッシュス化されて、データがある人もいるのかも知れませんが、いつも同じ人が同じ決済方法を使うとは限らないので、正確にはとれません。
少なくとも僕がコンビニで働いている時はデータがありませんでした。
なぜ「新規顧客」が増減したのか?
「新規顧客」分析 アプローチ数と購入率(受注率)
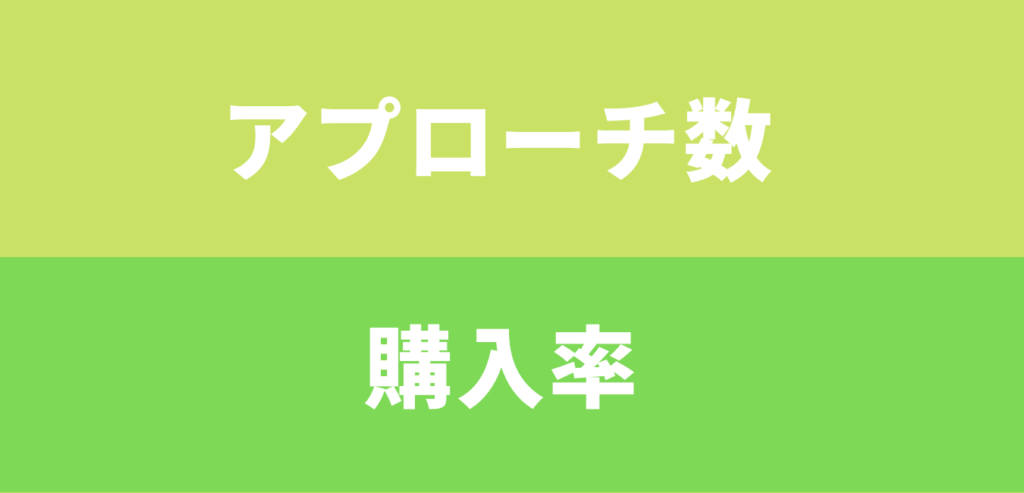
「新規顧客」増減する要因は「アプローチ数」と「購入率(受注率)」になります。
まだお店で買物をしたことがないお客様に、テレビCMやラジオCM、チラシやクーポン、アプリなどで、来店を促します。それが「アプローチ数」です。
コンビニの新店オープンの時は、この「アプローチ数」をどれだけ増やせるかで客数がとんでもなく変動します。従業員さん達に新店オープンのチラシをポスティングしてもらいます。新聞折り込みも入れます。
「購入率(受注率)」アプローチした人達が来店して、なにか買い物してくれるかどうかの率です。チラシとかCMを見て、お店に来て全員が買い物をしてくれると購入率100%です。でも、お店に来ない人もいますし、お店に来たけど、なにも買わない人もいます。
- 配布するチラシの枚数
- 配布するエリア
- お店の看板を見る人の数
- 看板を見た人のクチコミ etc・・・
アプローチ数に課題がある場合は、アプローチする人が足りない、プロモーションコストが足りない、アプローチする場所がズレて間違えている。などがあります。
買わなくても来店した人は「お客様」だと思うかもしれませんが、最初の公式を思い出してください。来店したけど、買わなかった人は売上にならないので、ここでは「客数」としてはカウントしません。
あくまで、買い物をした人だけを「客数」としています。本当は来店した人の数も取りたいのですが、当時は技術的に無理でした。今もまだ無理かもしれませんが、画像認識とかがないと数えられないんです。従業員さんや配送などの業者さんも出入りするのでなおさら難しいです。
レジを通った人しかカウントできないから、「客数=買い物の回数」という定義になっています。売上のところで少し触れた購入頻度も同じです。本当はデータとしては取れるに越したことはありませんが、データとして取れないので、1人のお客様が2回買い物をしたら、「客数は2」5回買い物をしたら「客数5」となります。
アプローチ数はわかりやすいのですが、「購入率(受注率)」は要因がいくつもあります。
- 競合店舗の立地
- 自店舗の立地
- 自店舗とオープンセールの割引対象の魅力度
- 来店時の品揃え、接客、清掃状況
- ブランド認知度とプレファランス
家の隣に競合店がある人はなかなか来店しない。そもそも家から遠い人や坂道を登るとかアプローチした人とお店の立地の関係が悪い。10円や20円の割引のために行こうと思わない。お店に来たけど混雑や、接客が悪い、汚いなどで買わない。そもそもブランドを知らない、嫌い。
なぜ「既存顧客」が増減したのか?
「既存顧客」分析 購入頻度と継続率
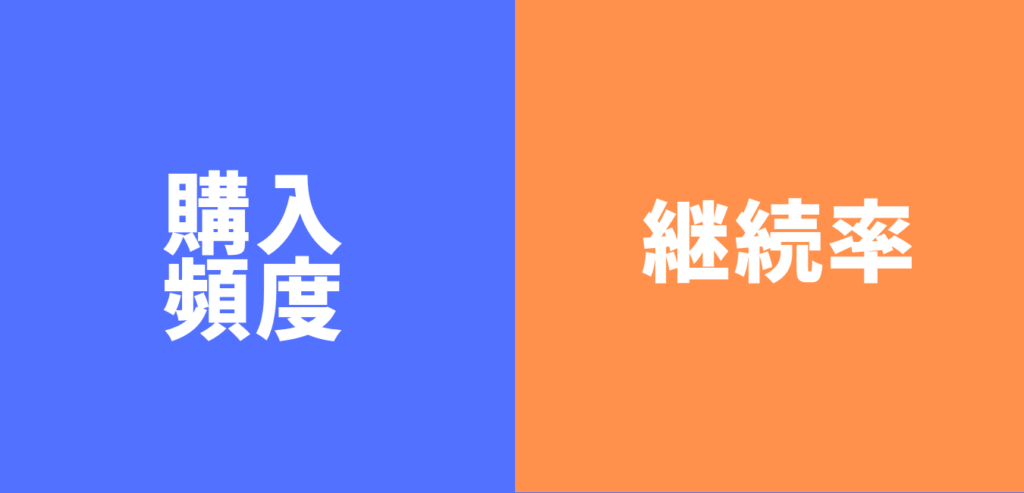
既存顧客は新規よりもわかりやすいです。1人のお客様が何回来てくれるか?と一度でも買い物をしてくれたお客様がどれくらい来てくれているか?です。
客数は1人のお客様が複数回買い物をすれば、複数回カウントするという説明を先程しました。1人のお客様が、朝、昼、晩、夜食まで買い物に来てくれれば4回来てくれることになります。これが「購入頻度」です。
「客数(既存顧客のみ)」100人だった場合でも以下のようなケースが考えられます。
100人が1回だけ買い物しているケース
50人が2回買い物をしているケース
20人が5回買い物しているケース
すべて同じ「客数100」になります。でも状況は全然違いますよね。
- 使用頻度が高い商品の品揃え
- 習慣の中で欲しい商品を品揃え
- 生活導線上に立地している
- 店員の接客、お店が清掃状況 etc・・・
一日に何度もコーヒーを飲む人が毎回買いに来る。朝はおにぎり、昼は弁当、夜はビールとおつまみを買いに来る。通り道にあるから立ち寄ってしまう。可愛い店員さんや愛想のいい店員がいる。トイレが綺麗。
一度でも買い物をしてくれたお客様がどれくらい来てくれているか?を「継続率」と表現しています。2回目以降に利用してくれているかだ。
「新規顧客」として来店した人が全員ずっと来店し続けてくれれば継続率100%になる。オープンの日に生活圏以外から遠いけど、セール目当てに来店したお客様とかは2回目の来店はほぼないだろう。
- 好きな商品の品揃え
- 好きだった商品が好きじゃなくなる
- 引っ越し・転職など生活圏の変化
- 競合の出店
- 店員の接客、お店が清掃状況 etc・・・
好きな商品がいつも売り切れたり、そもそも取り扱ってなかったりすると来店しなくなる。もっと近くて便利なところに競合ができてそれが同じチェーンだったら、来なくなる可能性は高い。
今回は購入頻度を1日、継続率を1ヶ月と考えていると仮定してください。
なぜ「客単価」が増減したのか?
「客単価」分析 購入点数と1商品あたりの単価
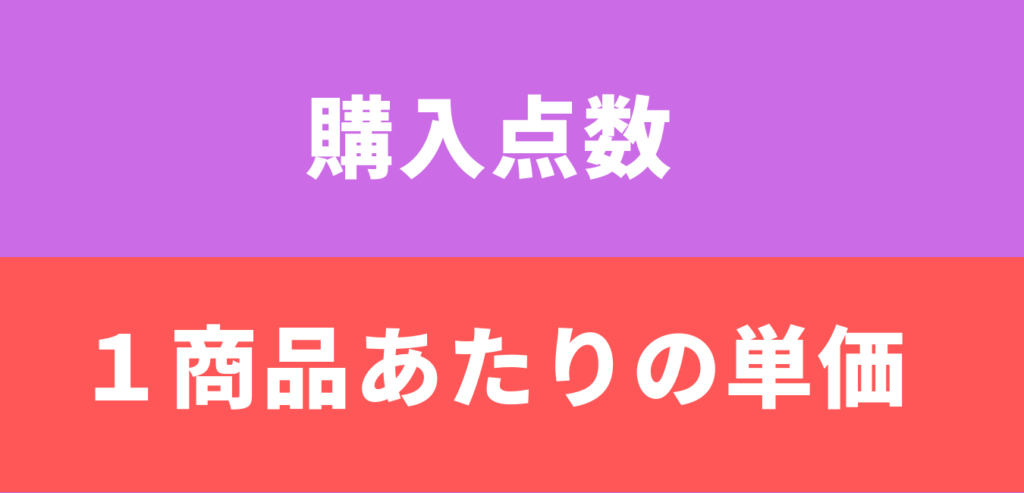
「客単価」は1人のお客様が、合計金額が何円の買い物をしたのか?を表した数字です。
1回あたりの客単価を合計したものが売上です。売上のところでも説明したとおり、客数=買い物の回数なので、客単価の算出のしかたは、売上÷客数=客単価となります。
1人のお客様にたくさんの金額を買い物してもらうことが、客単価UPになります。1個の金額は低くくてもたくさんの個数買ってもらえば、客単価はあがります。逆に1個しか買わなくても高い単価の商品を買ってくれば、客単価はあがります。
- 品揃え
- 関連商品の陳列
- 衝動買いを誘う陳列
- 声掛け販売・試食販売
- お届けや宅配サービス
- 事前予約
- etc・・・
おにぎり、お弁当、サンドイッチもパンも近くにありますよね?
目立つところに新商品を並べる。
レジの横には小さなお菓子がある。
たまに試食とか、「恵方巻きいかがですか〜」とか言ってる店ありませんか?
お届けは重い飲み物を高齢の人が買う時に持っていったりします。
町内会のイベントとかで、おにぎりの大量注文をもらったりします。
- 単価が高い商品の品揃え
- ワイン、日本酒、焼酎などの酒類の品揃え
- お中元やお歳暮、クリスマスケーキ、おせちなどの予約商品に注力
- ギフトカードを目立つところに並べる etc・・・
コンビニはあまり単価が高い商品がないのです。単価が高いの定義をどう考えるかが大切です。
そのお店の平均単価よりも1個あたりの単価が高い商品を品揃えすればOKです。コンビニの客単価の平均は600円〜700円くらいですので、それを上回っていれば客単価はあげられますよね。
ワインとか日本酒、焼酎などの酒類のボトルの品揃えを増やせばいいのですが、あまり売れないで微妙ですが、これも一つの手法です。
予約商品は単価が高いですが、たまにしかありません。1商品あたりの単価をあげるのは手法が少なく、お店が取り組むのは難しいです。
なぜ?を繰り返えしましょう!

ここまで、コンビニの売上が増減する要因を分解してきました。それぞれ対策しやすいところとしにくいところがあるのですが、気づきましたでしょうか?
客数と客単価では、客数を増やす方が対策しやすい。
アプローチ数の方が対策しやすい。
対策例)従業員を増やす・チラシの配布数を増やす・新聞折込の頻度あげるなど
継続率の方が対策しやすい。
対策例)常連がよく買ってくれる商品を品揃えする・他になにがあると嬉しいかを聞いて品揃えする。新しく好きなる商品を見つけてもらう(試食など)
購入点数の方が対策しやすい
対策例)入り口で買い物かごを配る・おでんは大きな入れ物に取る・試食や声掛け販売をする
対策のできるところをはっきりさせる
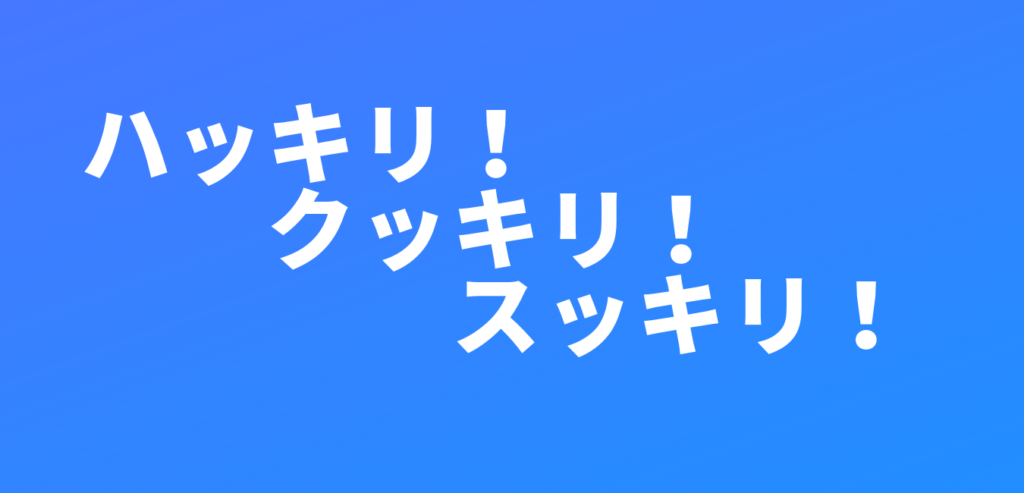
ここまで、なぜ?を積み重ねてきました、それは全部どこに対策を打つことができるか?を見つけるためです。
対策が打てるポイントをみつけて対策をして、その対策に効果があれば結果は改善されます。
対策できないところもはっきりします。
考えた対策を並べて、優先順位を決めることができるようになります。
インパクトより先に実現可能性
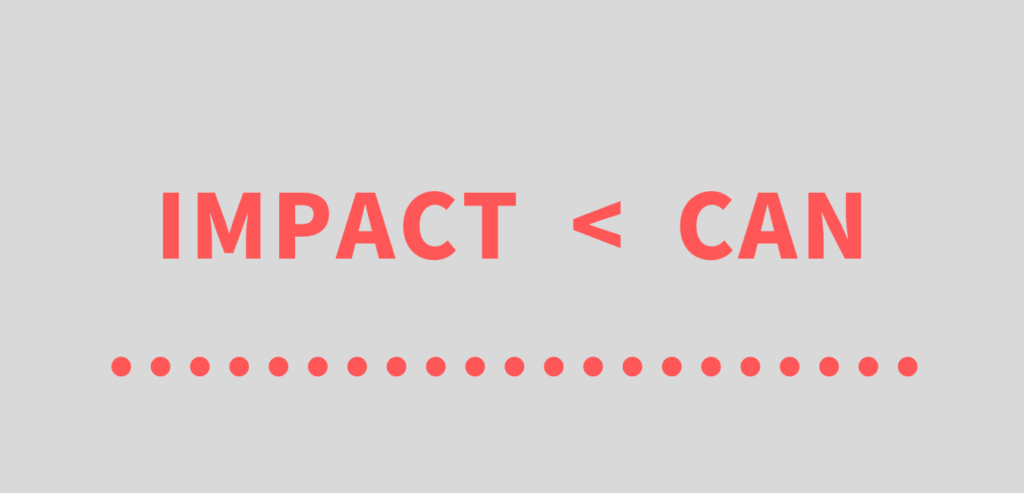
たくさん対策を考えて、さぁ優先順位を付けましょう!となります。その時に感覚で優先順位を付けてしまいがちですが、それだと頭が途中でぐちゃぐちゃになります。
オススメの優先順位の付け方は、3つの項目で10段階のポイントをつける。
- 実現可能性:対策を実行できるかどうか?夢のような対策ではないか?
- インパクト:売上に対するインパクト
- 効果速度:効果が短期間で出るのか?中長期的になるのか?
この3項目の合計点が高い対策に取り組んでいきますが、一番重要なのは、「実現可能性」です。
| 対策 | 実現可能性 | インパクト | 効果速度 | 合計ポイント |
| A | 3 | 7 | 10 | 20 |
| B | 10 | 5 | 5 | 20 |
対策のAとBは合計ポイントは同じ20ですが、バランスが異なります。
効果速度を見れば、対策Aの方が早く効果が出るので魅力的です。
インパクトも対策Aの方が高く、売上も対策Bより上がりそうです。
逆に実現可能性は対策Aが低く、対策Bが高いので、対策Bは実現できるイメージが湧いています。
さて、対策Aと対策Bどちらに取り掛かるべきだと思いますか?
対策Aは実現可能性が3とかなり低く、実現できない可能性が高い対策です。
対策Bは実現可能性が10と高く、ほぼできそうだと予測できています。
実現できそうにないものに取り組むよりも、実現できそうな対策Bを終わらせてから、対策Aに取り掛かるべきです。
実際には組織の状況によって優先すべき軸が実現可能性ではなく、変わることがあります。基本的に実現可能性が高い対策が優先で問題ないと思います。
数字を上げます!だけでは答えが足りない
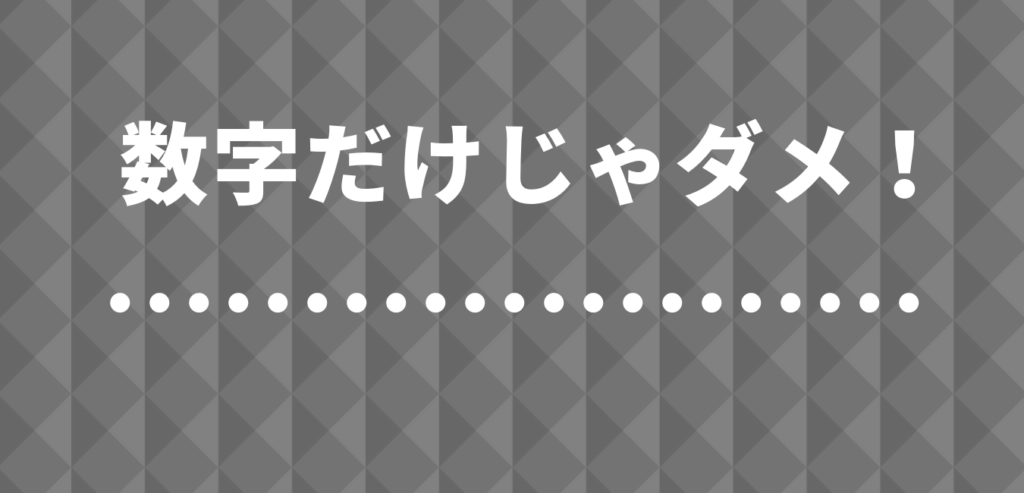
客数を50人増やします!客単価を50円上げます!しっかりと取り組んでいきます。みたいな報告をする人がいますが、これでは報告内容が足りません。
最低でも、どうやって?といつまでに?が必要です。
増える50人のお客様は「新規顧客」?「既存顧客」?
「新規顧客」ならアプローチ数を増やすの?購入率を上げるの?
どうやって?いつまでに完了させるのか?
付け加えるのであれば、どうやって、いつまでにそれをやると、
なぜ?50人新規顧客が増えるのか?
まで説明できるとなお、良い報告になります。
まとめ
多くの人は、答えのない問いを考え続けてしまいがちです。それは原因だけを探そうとしているからです。
自分の行動で対策が打てない原因は考える必要はありません。それは変数です。不可抗力に近い。自分が行動することで影響を与えられる原因に対策を立てましょう!
今回のご紹介した手順で、原因と対策を考えて、報告をすれば、きっと上司から詰められることは少なくなるでしょう。あなたの上司が理不尽な不可抗力をなんとかしろ!という上司でないことを願っています。
最後に僕の恩師からもらった金言です。
 Simple WORK
Simple WORK