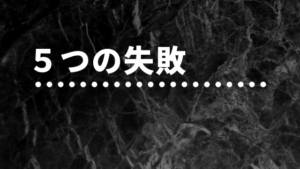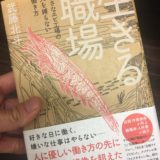初めてマネジメントをすることになったはいいけど、「マネジメント」ってなんだろう?
先輩や上司にドラッガーを読むといいと言われて、読んだけど、わかったようなわからないような・・・
昔の自分がそうでした。
コンビニの店長時代に初めて副店長で部下がつきました。その時は試行錯誤、悪戦苦闘しながらも、なんとか結果もだし、部下も育てることができました。
しかし、
その後、別の会社でマネジメントする時に困ってしまいます。あれ?なにすればいいんだっけ?となってしまいました。
そこから、いろいろな書籍を読み漁り、勉強をしてなんとか、かんとかやってきましたが、いつもマネジメントの本を読む度にいつも”何か違う”と違和感がありました。
「マネジメント」という言葉の意味が広義であり、書籍によって「経営者向け」「中間管理職むけ」「現場リーダー向け」また、想定している業種も様々な例えがあるか、逆に抽象的過ぎてわからない。
そのよくわからない状況を整理する考え方は以外にシンプルで「役割」「権限」「責任」「ルール」「評価」この5つのポイントに絞ればわかりやすくなります。
目次
そもそもマネジメントってなんだっけ?
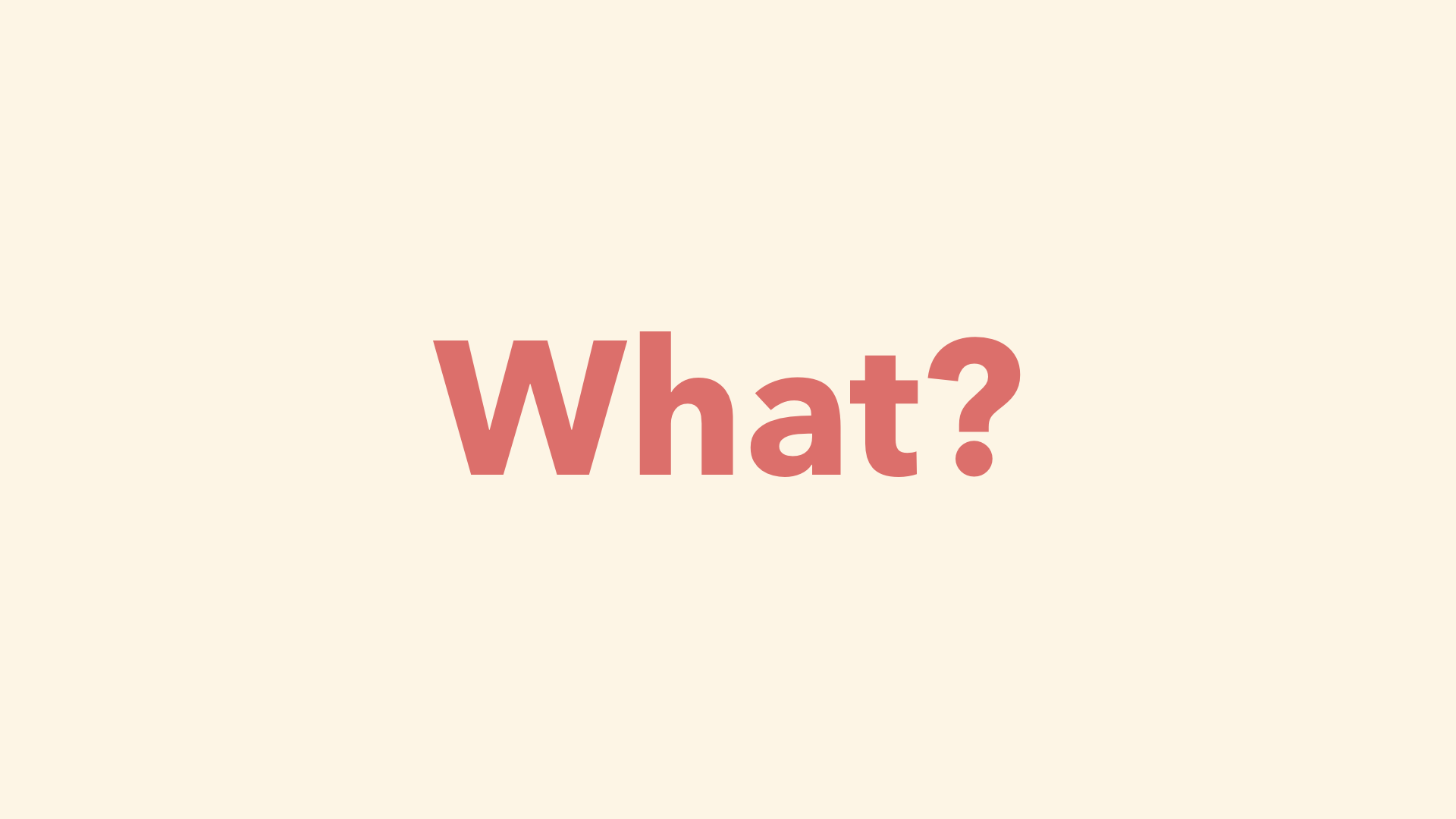
ドラッガーのマネジメントの定義
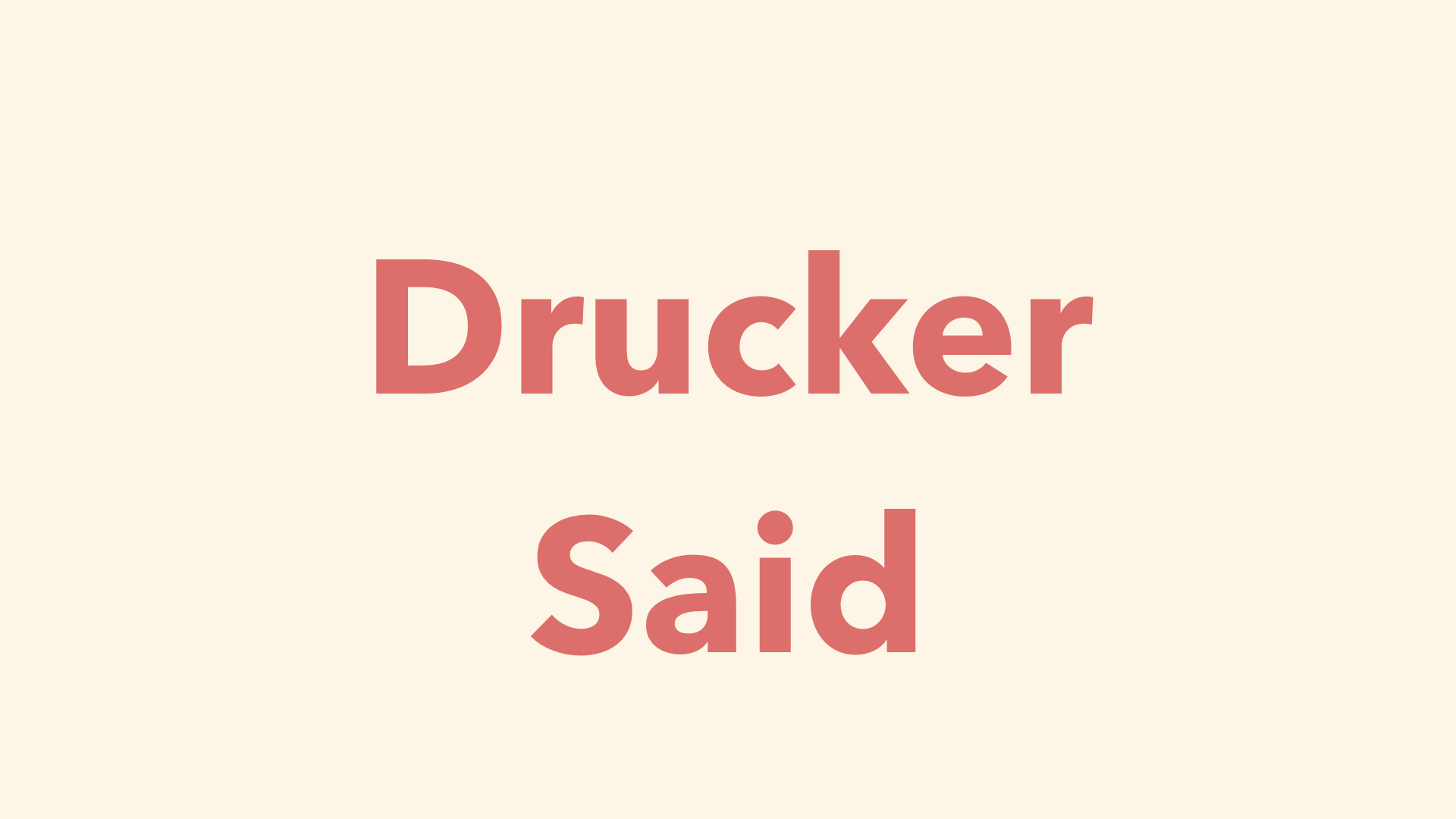
マネジメントの生みの親であるピーター・F・ドラッガー(Fはフェルディナント:豆知識)がマネジメントを以下のように定義しています。
組織に成果を上げさせるための道具、機能、機関
広義に適用できるように、抽象化された言葉で書かれている。これがわかるようでわからなくしている原因でもある、少し具体的に書いてみます。
- 組織=会社、部署、課、グループ、チーム
- 成果=予算、売上、経費、利益
- 道具=物差し、目標を明確にする道具
- 機能=方針決定、役割分担、進捗管理
- 機関=株主総会、取締役会、軍司令部
著書によって、書いてあることが変わっているので、え?これじゃないでしょ?と思う方もいるかもしえれません。
SimpleWORKなりのマネジメントの定義
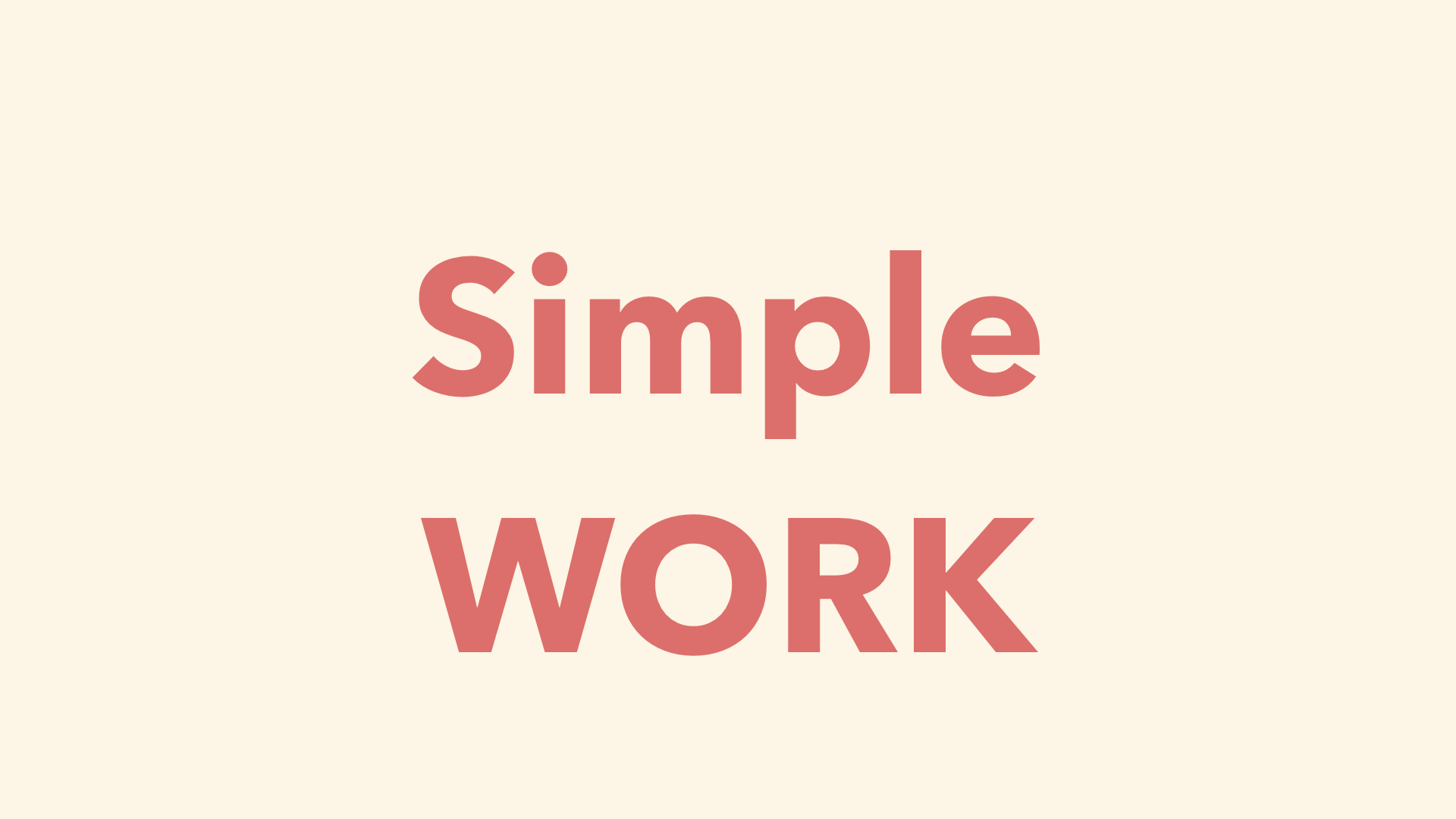
わかりやすくしようとしたのですが、逆にわかりにくくなってしまいました。結論は「組織の目標を設定して、その目標を達成する為に、必要なこと全部」になります。
つまり広義に捉えると経営とほぼ同義になります。
でも、初めて部下を持ったばかりなのに、経営なんてできません。いろんな本を読んでも自分には関係ないなと思う記載が多いです。
マネジメントする範囲や与えられている権限、役割が違うとマネジメントが果たす機能が違うからです。
勉強しようと意気込んで本を読み始めたものの、今の自分の立場ではどうしようもないことが出てくるので、読む気をなくしてしまった本が本棚にありませんか?
初めてマネジメントの時にどういったことを考え、学べばいいのかがわからなくなってしまいます。
一冊の本でも、経営側に必要なマネジメントと現場よりのマネジメントが入り混じっているものも多いです。
ちょっとこれは自分の範疇じゃないと思うところを飛ばして、すぐに役に立ちそうなところだけ読んでしまうことをオススメします。
定義が広義で曖昧なので、もう少し具体的にマネジメントを捉える必要があります。
マネジメントは抽象的で曖昧?
マネジメントを難しくしてる原因

「マネジメント」という言葉は、少し偉くなった気分になるし、難しいことをしている気分になります。子供の頃に、大人の会話に入れた時に感じるような気分を少なからず味わうことがあります。
管理職だけの飲み会で部下について話して、「マネジメントって本当難しいよね。答えがないよ」というような会話している人もいます。
なぜ、難しいと思うのか?「ハッキリしていないこと」と「流動的な部分」があるからです。
多くの企業でよくあることなんですが、マネジメントを難しくしている要因は、「役割と権限」が曖昧なままだからです。これが”ハッキリ”していないとどこまでなにをやっていいのかがわかりません。
「会社から期待されている役割」と「会社から与えられている権限」
逆に”ハッキリ”していることもあります。それは、「期待されている数字に対する責任」です。これだけはハッキリしている会社が多いです。
でも、それ以外に求めている「役割」と「数字に対する責任を果たす為の権限」は曖昧なことが多いです。
もう一つのマネジメントを難しくしている原因の「流動的な部分」です。これはなにを表しているかというと「部下と上司の仕事とスキルと感情」です。変化が激しい業界で、朝令暮改がよくある会社では「戦略」も「流動的な部分」にはいります。
まず、部下から考えてみましょう。部下は往々にして若い場合が多いです。若い人は成長が著しいです。それまで成長が止まっていると思っていた人が急になにかきっかけを掴んで成長をすることもあります。
こないだまで期限内に終わらなかった仕事を終わらせてきたり、ミスが減っていたり、資料のクオリティが上がったり、提案の質が上がったり、と成長をしていきます。それと同時に、恋愛、同僚と合う合わない、といった「感情」の変化も激しいです。もちろんそうじゃない人もいますが、その傾向が強いです。
部下のスキルに合わせて仕事を分担したり、再分担したりします。感情によって完成度が変わったりします。それが部下の「流動的な部分」です。
次は上司です。上司が変わるタイミングは会議やMTGの後が多いです。事業の方針や戦略が変わる、上司の上司からの指摘で変わる。上司の流動的な部分は「指示の内容」「指示の仕方」「報告の聞き方」「注目するポイント」がかわります。これは上司としてのスキルにあたる部分です。
部下に対する感情も流動的です。今まで成果が出せなかった部下が成果を出したら一気にプラスの感情が強くなることもあります。その逆もあります。
会社以外でも家庭がある方だと、家庭での状況を引きずることもあります。朝から機嫌が悪いとか、最近元気がないなどがあります。これは「感情」が揺らいでいることになります。
部下は「成長と感情」、上司は「会社からの評価と感情」これが「流動的な部分」です。
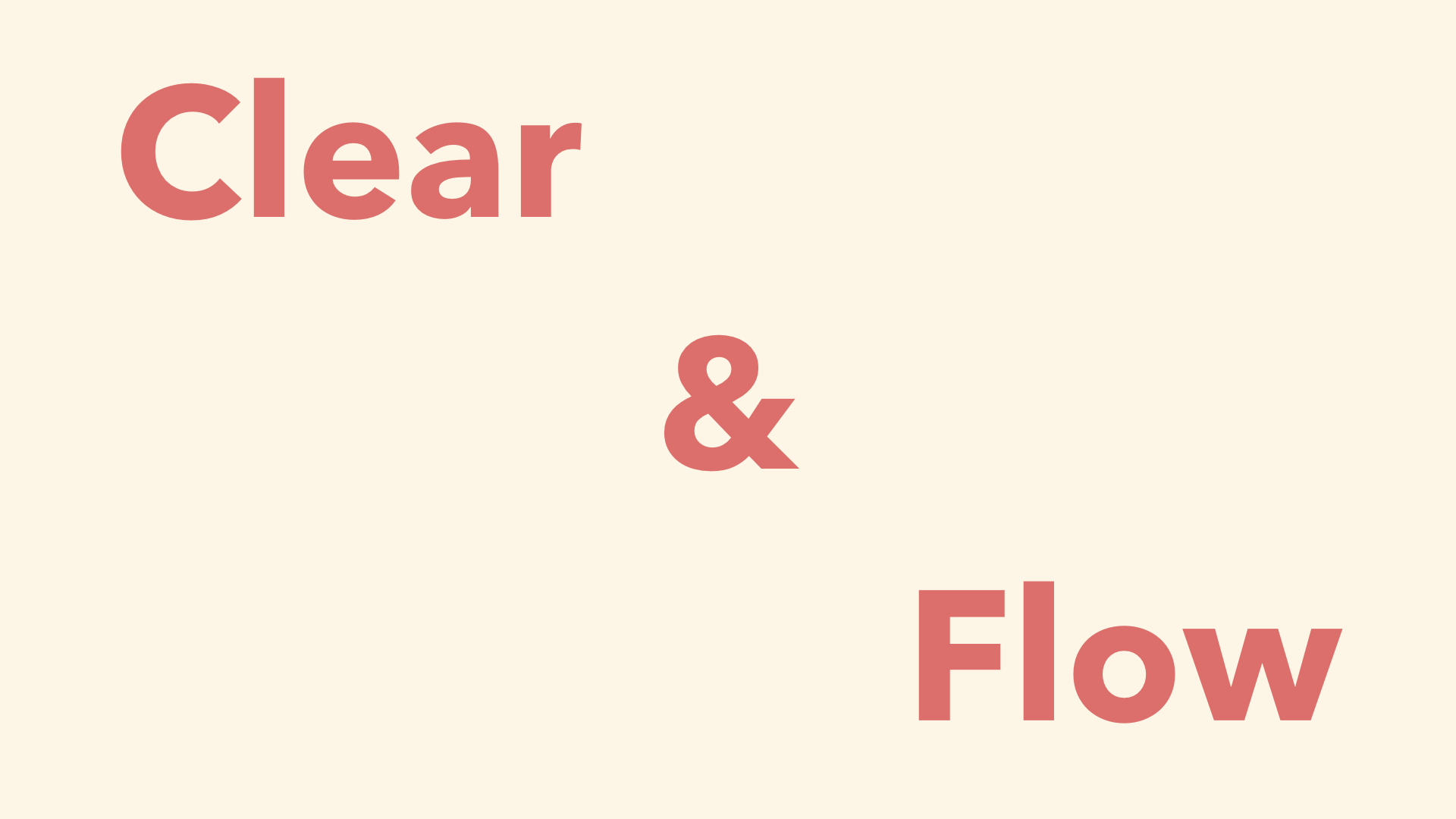
「ハッキリしていないこと」を解決する方法
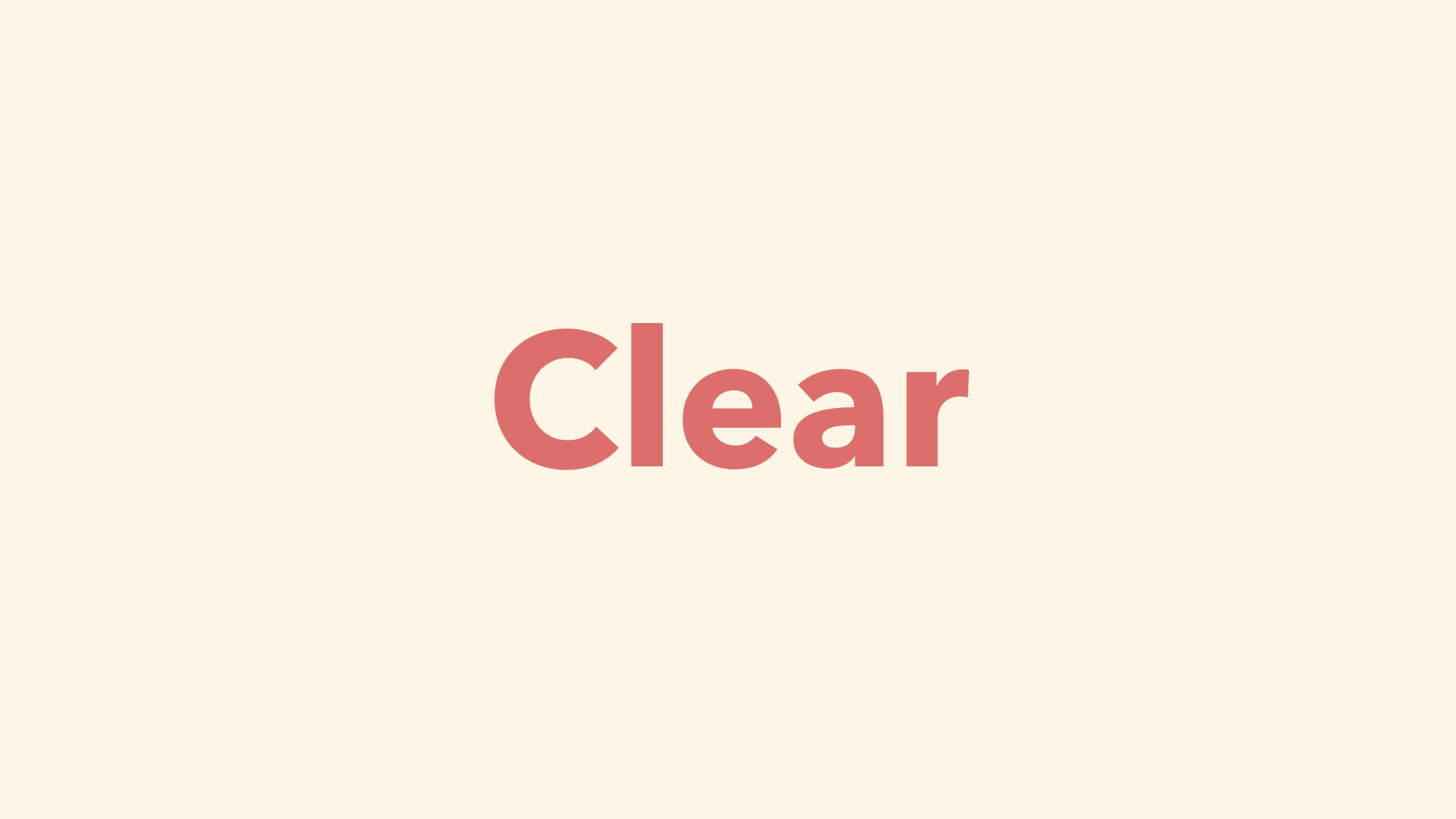
「ハッキリしていないこと」は、この2つ「会社から期待されている役割」と「会社から与えられている権限」です。
これをハッキリさせるのは簡単です。上司に確認しに行きましょう。上司も決めれない可能性がありますが、その場合は、「自分がどこまで決めますからいいですね」のイエスを取りにいきましょう。
多くの場合、決められている役割と権限は最低限はこれだと思います。
- 役割:部下の目標を達成する・部下を育成する
- 権限:部下と自分の労働力を使う・会社で認められている営業経費
この時に、権限をたくさんくださいと話してしまう人がいます。部下を持っているのだから、これくらい権限があってもいいと思ってしまいます。
なぜ権限が与えられているのか?を忘れてしまうからです。あくまで、権限は「数字に対する責任を果たす為の権限」であり、大きな権限をもらうとその分、大きな数字責任を果たす必要があります。
必要以上の権限を求めると、それは数字責任が増やすことにもなります。権限と責任は比例関係にあることをわきまえた上で、上記に記載した最低限の権限以上の権限を取りに行きましょう。

「流動的な部分」を解決する方法
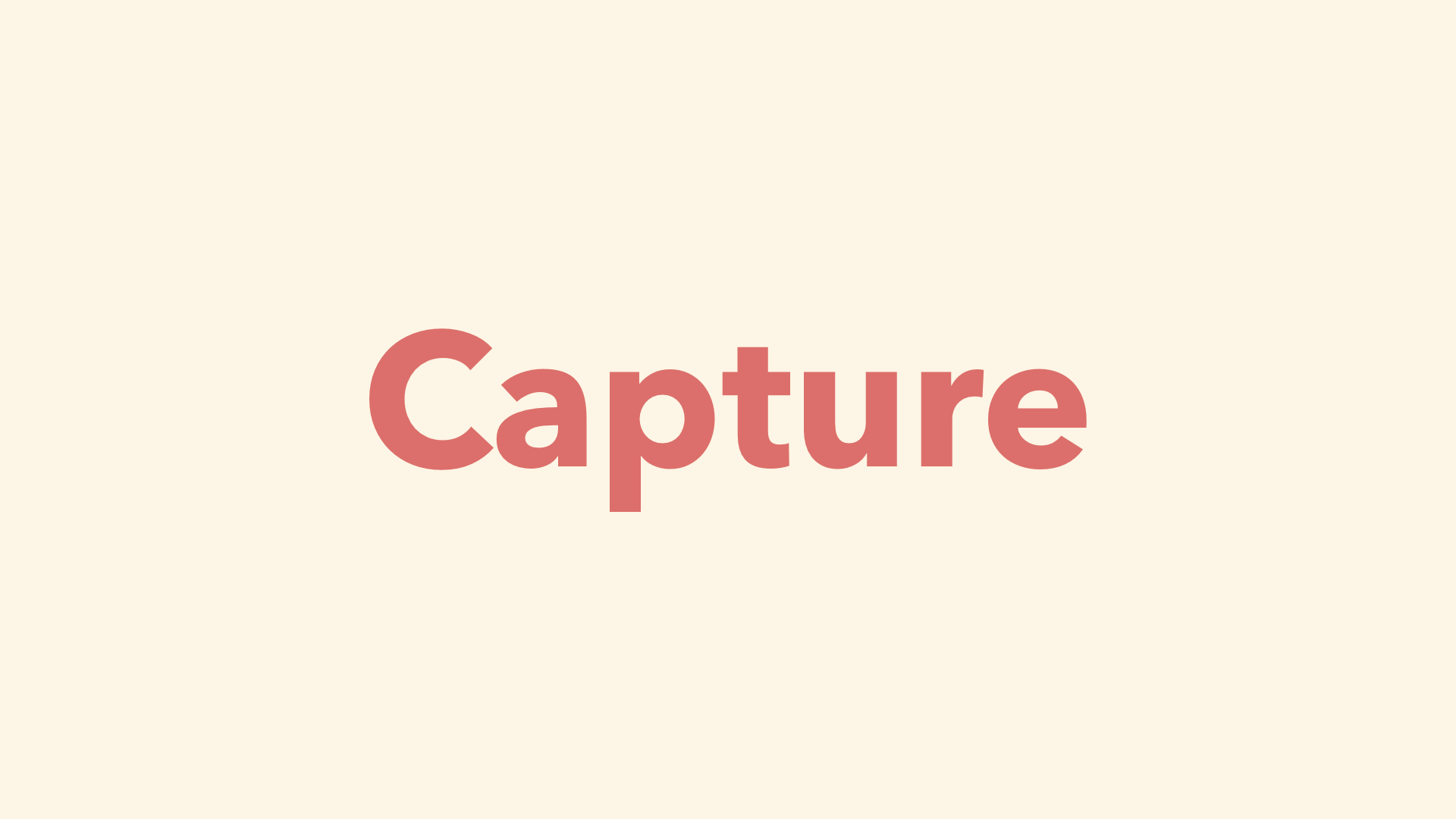
マネジメントを難しくしている一番の原因が、これと言ってもよいと思います。人のスキルと感情が流動的で捉えにくいからです。
それを把握するために必要なことは定期的な対話です。最低でも週に1回、1対1で上司部下が話すことが必要です。
最近流行りの1on1をやりましょう。そこで話すべきはまず、上司である自分のことです。上司である自分がどういう傾向の感情を出すことがあるのか?を先に話してしまいます。
普通の1on1のやり方を解説しているサイトや本は、部下の話しを聞きなさいと書いてあります。部下が上司のことを理解したら、部下の話しを聞く時間を多くした方がいいです。
なぜか?
部下は上司の顔色をうかがいます。それはどんなに気さくに接していても少なからずあります。上司である自分の顔色を正しく把握してもらうことが必要です。そして、上司がどういう人間かわかれば、部下も話しやすくなります。
上司がオープンにしていないレベルの深さのところまで、自分から進んで話してくれる部下は少ないです。
1on1に関しては別途くわしくやり方を説明したいと思います。
そして、複数メンバーがを抱えている場合は、メンバー同士の相互理解も重要になります。
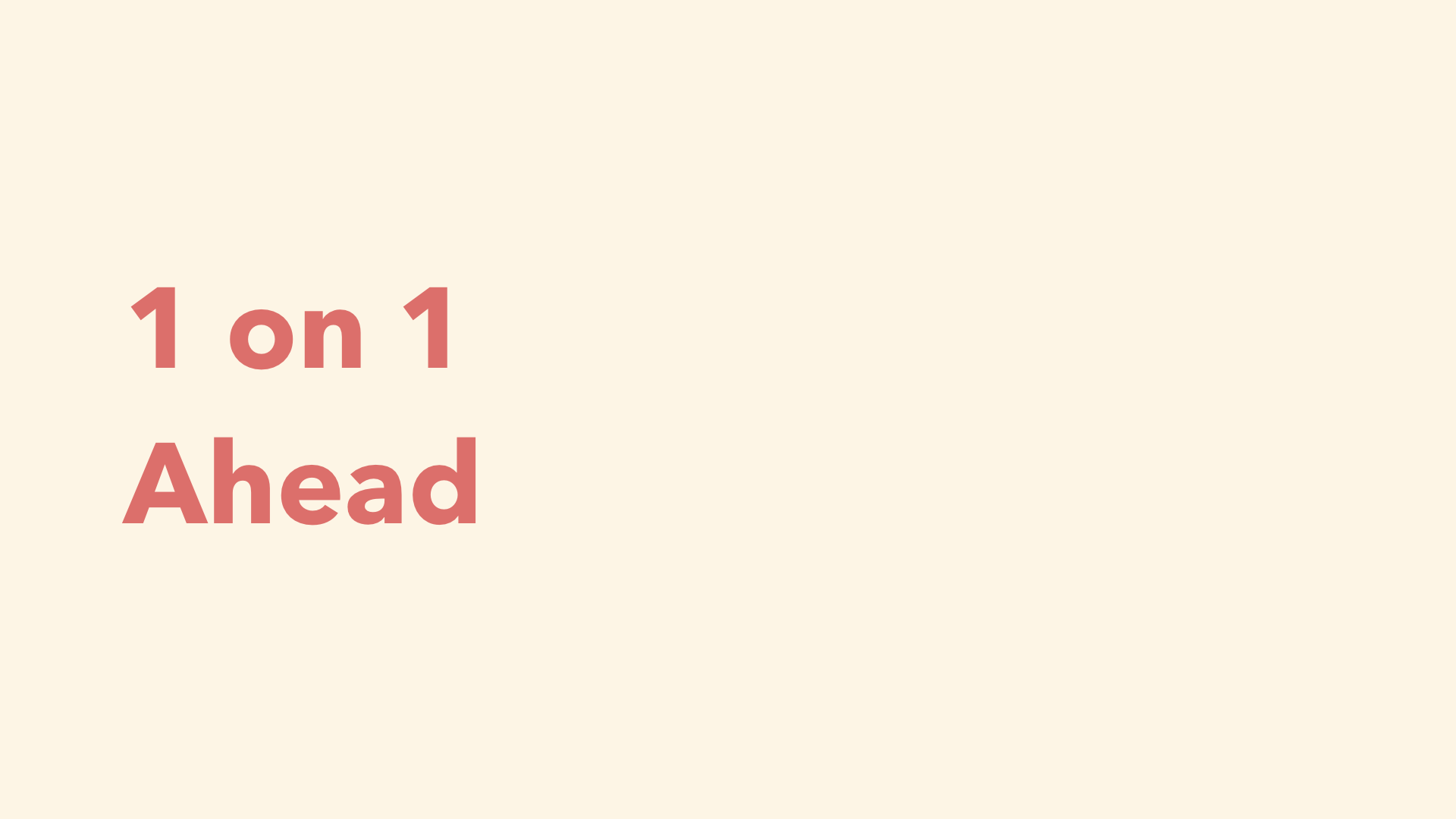
マネジメントが上手い人はルールを作るのが上手い人
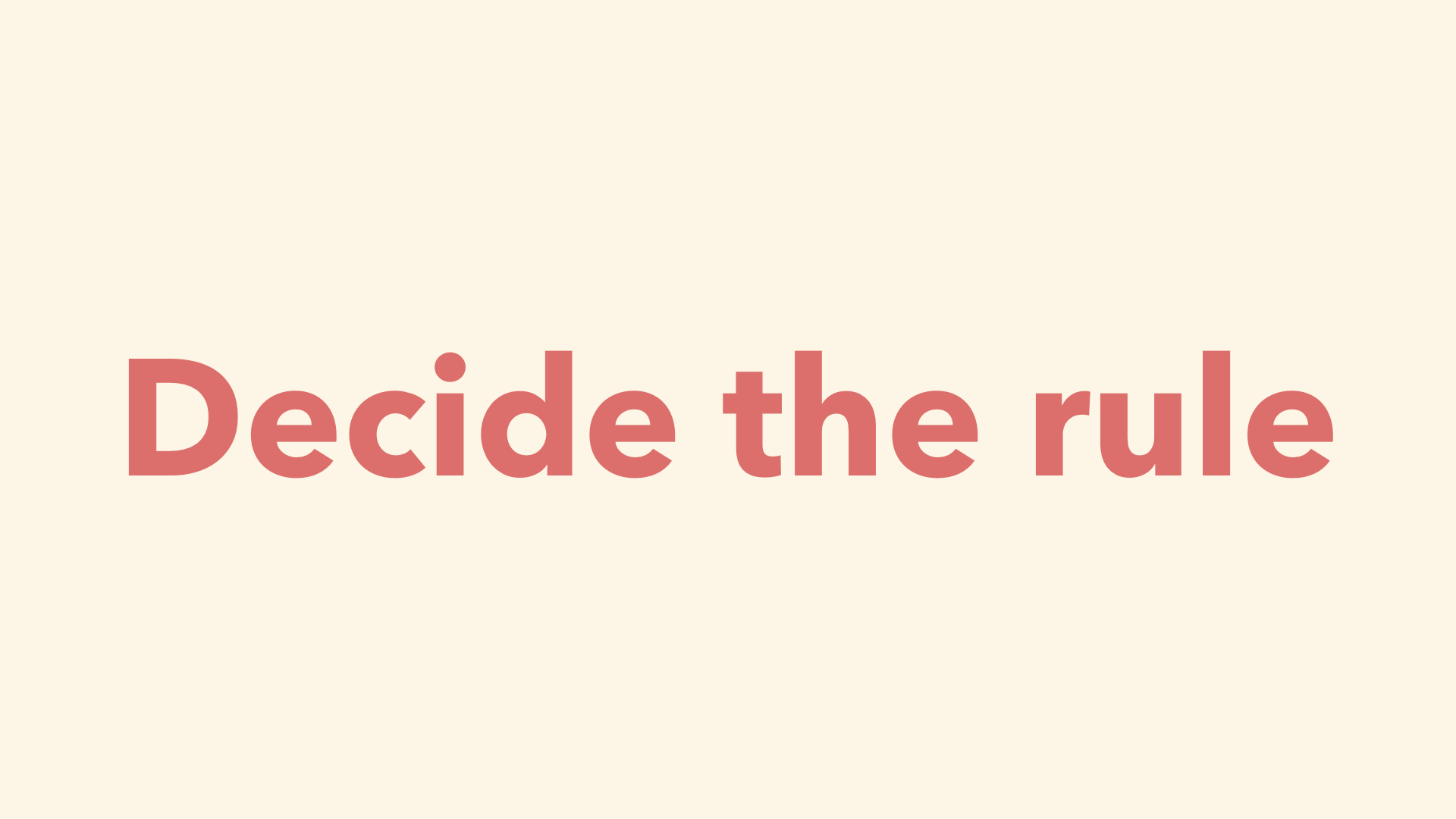
「流動的な部分」は相互理解によって、感情の部分はかなり把握できるようになります。では、相互理解を深める為に、なにをしなければいけないのでしょうか?
嫌悪の感情を発生させないことが大切です。嫌悪感を抱いていなければ、拒否はされないです。好意までは難しくても、嫌いにならないことはできます。
嫌いになる人はこういった言葉を言います。
「あいつはいつも楽をしている」
「仕事が遅い」
「あいつができてないからフォローしてばかりいる」
この言葉が表している事はなんでしょうか?
「あいつはいつも(自分より)楽をしている」
「(自分より)仕事が遅い」
「あいつができてないから(自分が)フォローしてばかりいる」
基準が自分です。そして、自主的に役割以上のことをやっているけど、評価されない。という不満が裏にはあります。
チームの中での「ルール」として明確に指示していれば、それが「評価」につながることになります。評価するとほとんどの場合、不満が消えます。
ただし、このルールが後付になのはよくありません。できるだけ前もって予測して指示しておくことが大切です。
後付でルールを決める場合は、きちんと説明が必要です。
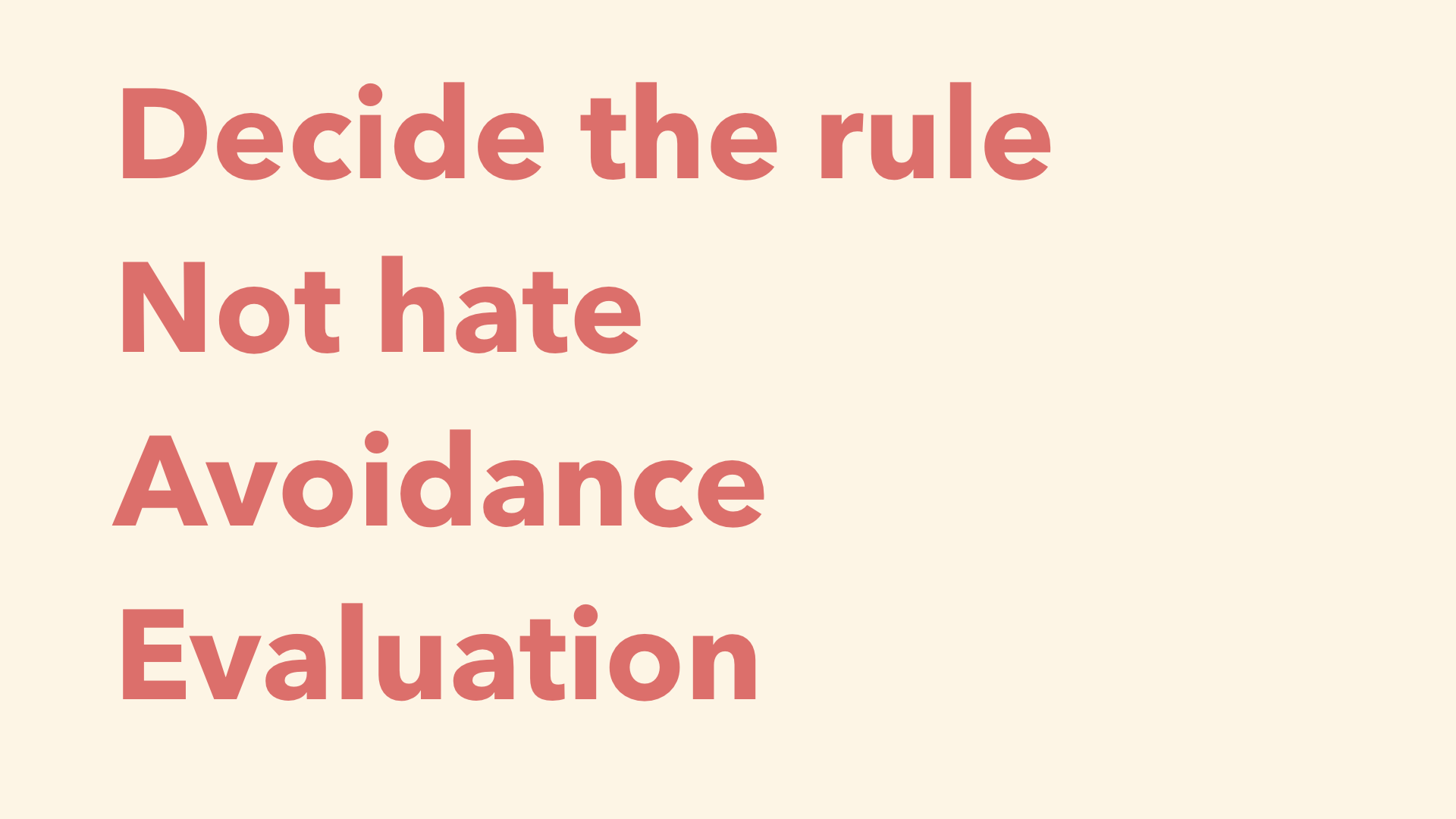
まとめ

- マネジメントは広義すぎる
- マネジメントを難しくしている原因は「ハッキリしてないこと」と「流動的な部分」
- 「ハッキリしてないこと」は「会社から期待されている役割」と「会社から与えられている権限」
- 「流動的な部分」は「成長」「会社からの評価」と「感情」
- 役割と権限は上司に確認しにいく
- 週1回の1on1で、自分の心を開く
- メンバー内のルールを設定して、それを評価する
 Simple WORK
Simple WORK