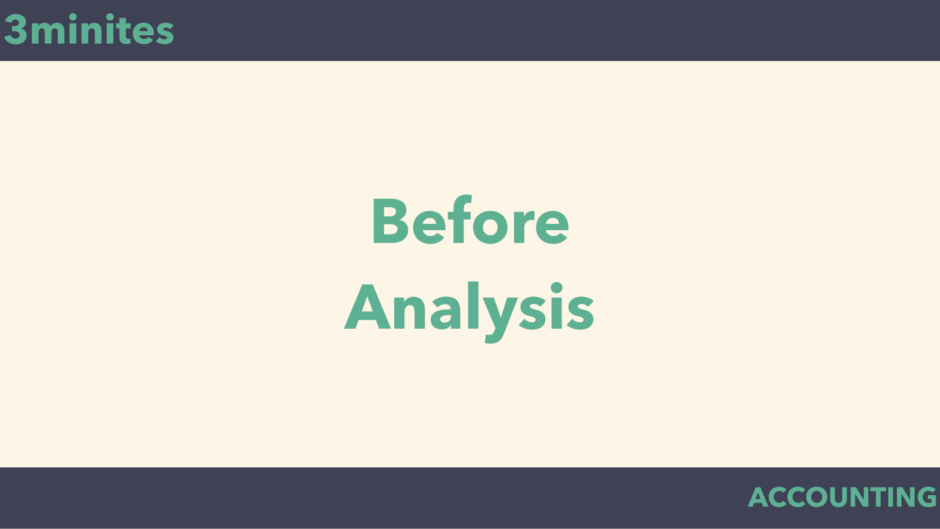企業活動の成績表は財務諸表です。財務諸表は「なにを目的に見るのか?」によって、分析軸は変わります。投資家、経営者、従業員によってそれぞれ味方や見る目的が違います。
この記事では分析手法の詳細を説明する前に、分析に必須である「比較法」について説明しています。
比較しないと良いのか悪いのか?が、わからないことが多いです。比較していないことでもなんとなくの基準を持っている事が多いです。
例えば、男性で身長180cmの人は背が高いと思いませんか?それは自分の身長や今までに会った背の高い人のイメージを思い出して比較しているから、背が高いと思います。
体重も同じです、男性で身長160cmで体重90kgは太っていると思います。身長と同じで自分や他の誰かと比較して判断しているのです。
企業もそれと同じです。売上100億、営業利益5億 営業利益率5%と言われてもこれが高いのか?低いのか?の基準や比較対象を持たないとわからないです。
比較対象として、3つ上げています。期間比較、相互比較、標準比較について説明していきます。
財務諸表を見る時の3つの比較方法

財務諸表は、貸借対照表(B/S)損益計算書(P/L)キャッシュフロー計算書の3表が主がであることとそれぞれがなにを表現しているのか?は以前の解説しました。
まだご覧になっていない方はこちらをどうぞ↓
関連記事のIDを正しく入力してくださいそれぞれの各項目の詳細な説明はここではしません。それよりもなにがわかるから重要なのか?を理解できるように説明していきます。
期間比較法

同じ会社の財務諸表を、異なる期間で比較する方法です。主に比較されているのが、今年と去年の同じ時期と、四半期毎に今四半期と前四半期との比較です。
日経新聞でもよく出てきますが、前期と比較し前年比と表現されます。四半期で比較している時は前期比というような表現を使ったりします。
同じ会社が時期によって、良くなっているのか?悪くなっているのか?をわかることがこの期間比較法の良いところです。
逆に同じ会社のことしかわかりません。どちらかというと内部分析に用いられることが多いです。
内部分析とは会社内の課題や問題点を把握し対策をするための分析です。
相互比較法

期間比較法では、前と後でどう変化しているのか、がわかりました。
でも、その数字自体が良いのか?悪いのか?はわからないです。
それを明確にするのが、相互比較です。
人材紹介事業をしているA社とB社があるとします。
A社 前年度 売上5億→今年度 売上10億 前年比200%
売上が著しく伸びているので、すごく良い!と言えるかもしれません。
では、競合他社が以下のような場合
B社 前年度 売上5億→今年度 売上50億 前年比500%
とんでもない売上伸長をしています。
去年までは同じ売上だった競合と売上で5倍差が発生してしまっています。この状況でもA社の成績はすごい良かったと言えるでしょうか?
どこか他の会社と比較して、どこの数字が違うのか?どれくらい違うのか?ということがわからないと、1社の数字が良いのか悪いのかを判断することが難しいです。
財務諸表に書かれている数字や計算した数字が良いか悪いかは時期の比較だけでなく、競合他社の数字を見比べてみることで判断しやすくなります。
標準比較法

これまで、期間で比較する期間比較法、競合他社と比較する相互比較法を解説してきました。もう一つ重要な比較法があります。それが標準比較法です。
人材紹介事業をしているA社とB社があるとします。
A社 前年度 売上5億→今年度 売上10億 前年比200%
B社 前年度 売上5億→今年度 売上50億 前年比500%
上記のような結果でした。
人材紹介業界の平均の推移
平均 前年度 売上10億→今年度 売上30億 前年比300%
A社は業界平均よりも低い成長率であり、売上額も平均以下
B社は業界平均よりも高い成長率であり、売上額も平均以上
上記のように、業界平均と比較すると数字の良し悪しが更にわかりやすくなります。
業界平均の売上が開示されるようなことはほぼありませんので、矢野経済研究所のようなところが発行している資料などで確認するのが信憑性が高いです。
もしくは、いくつかの業界の上位3位までの企業をターゲットにして前年伸長率を比較するということが良いと思います。
財務諸表以外でも使える!
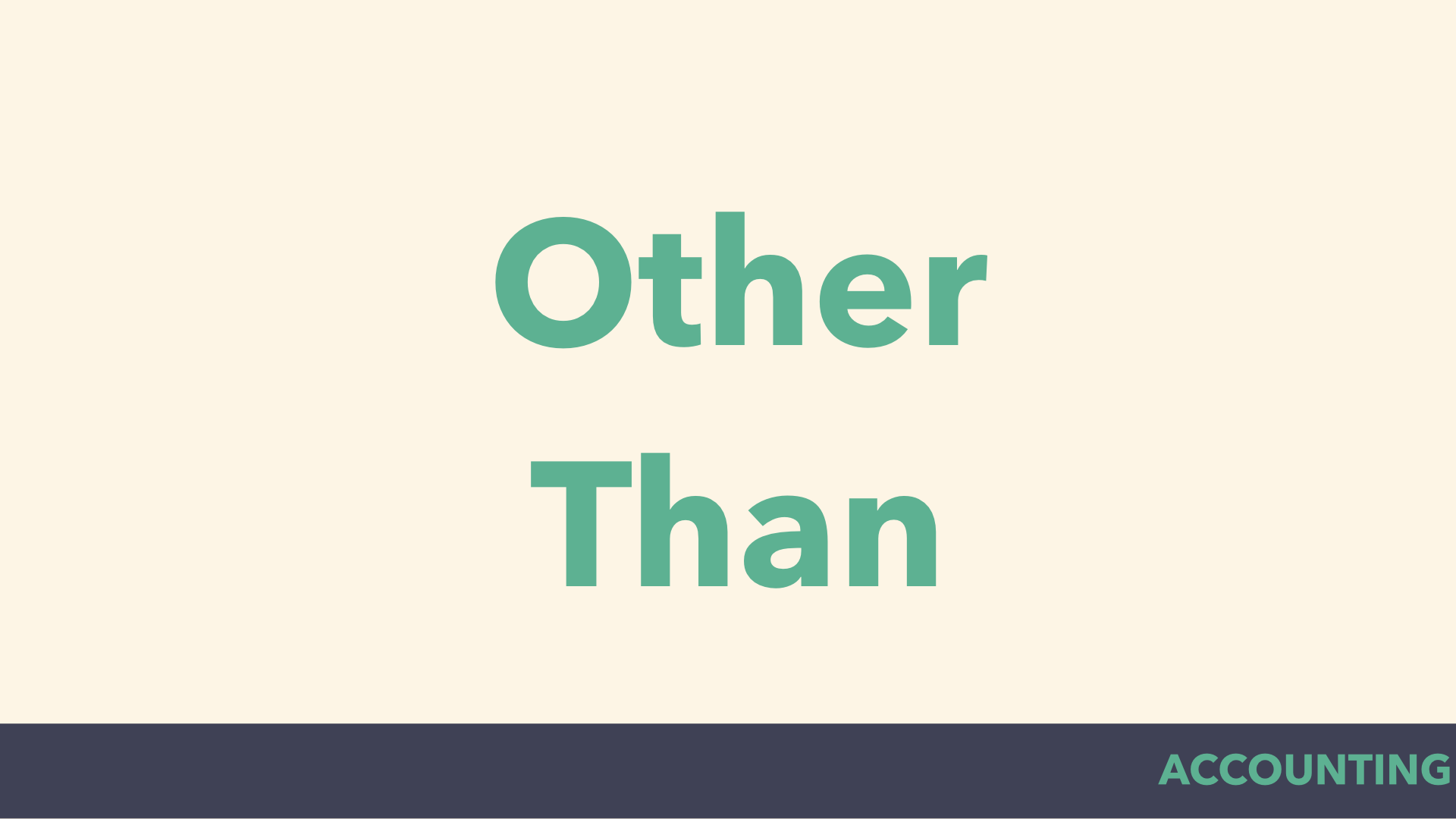
一つの数字だけを見て、高い低いと論じることは難しく、すでに基準がある事以外では良し悪しは判断できないことはわかっていただけたと思います。
この3つの比較法は他にも転用できます。
個人の売上も、サイトのPV、アプリのユーザー数も、この3種類の比較をすることで、状態が良いのか?悪いのか?は把握できます。数字分析における基本的な考え方です。
財務分析を分析してなにがわかるのか?

財務分析をしてなにがわかるのかということが重要です。
収益性、効率性、安全性、生産性をみる。
シンプルにいうと、利益はでやすいのか?売上は上がりやすいのか?倒産しにくいのか?生産性は高いのか?を知るために分析します。分析手法で主要な分析は4つしかありません。
- 収益性分析
- 効率性分析
- 安全性分析
- 生産性分析
この4つの分析が主なものになります。詳細はこの記事では触れませんが、概要を説明しておきます。
収益性分析
企業の収益獲得の能力を表します。利益と資本、利益と売上を計算し指標をだして分析します。
効率性分析
効率性分析は資本の使用効率の分析です。投資した資本がどれだけの売上をもたらしているのか、また、その期間を表す指標を出す分析です。
安全性分析
安全性分析は、企業の支払能力や財務面での安全性を分析するための手法です。
生産性分析
生産性分析は、生産諸要素がどれだけ効率的に生産に寄与したのかを分析する方法です。
まとめ

指標や比較できる数字がないと、その数字が良いか悪いかは判断できません。期間比較法、相互比較法、標準比較法を使う事で、良いか悪いかが判断できるようになります。
どこがどれだけ悪いのか?良いのか?がわかって、原因と対策が打てるようになります。原因がわからないのに、対策たてると的はずれな対策を立ててしまう可能性があります。
分析に前に、P/L、B/S,キャッシュフロー計算書の各項目を理解することが必要です。でも裏技もありますので、今度そちらを解説したいと思います。
 幹部はみんな知っている財務・会計の基礎知識が3分でわかる【初級編】
幹部はみんな知っている財務・会計の基礎知識が3分でわかる【初級編】
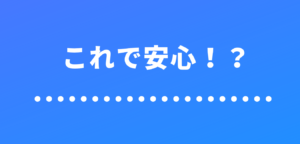 モチベーションに繋がる|もう上司に怒られない!原因と対策の報告のしかた【ロジカルシンキング】
モチベーションに繋がる|もう上司に怒られない!原因と対策の報告のしかた【ロジカルシンキング】
 Simple WORK
Simple WORK