チームワークの良い職場は理想的だと思います。できればそういう職場で働きたいと思うのは自然なことだと思います。
チームワークの良い職場とは、どんな職場なのでしょうか?
目標を達成する職場でしょうか?
メンバーの仲が良い職場でしょうか?
誰もが一所懸命働いている職場でしょうか?
メンバー同士が称賛し合う職場でしょうか?
毎日みんなが楽しい職場でしょうか?
「チームワークの良い職場」という言葉の捉え方や想像している事は、人によってイメージが違うと思います。
でも、逆に「チームワークが良くない職場」のイメージは良い職場に比べると同じような価値観で話しができるものです。
この記事では、チームワークの良い職場にする為に、チームワークが悪くなる要因を減らすことを提案しています。
チームワークを悪くする要因の一つである、「社会的手抜き」の原因と対策をご紹介します。この社会的手抜きについては、THE TEAM 5つの法則 要約 著:麻野耕司 感想まとめ その3の中で「チームの落とし穴」として紹介されています。
それだけチームを機能不全にしてしまう悪影響が大きいことになります。
この記事を読めば、チームワークが悪くなる原因を一つなくすことができるので、チームワークの良い職場に一歩近づけると思います。
目次
チームワークの良い職場づくりを阻害する「社会的手抜き」とは?
怠けている人がいるチームはチームワークが悪くなる
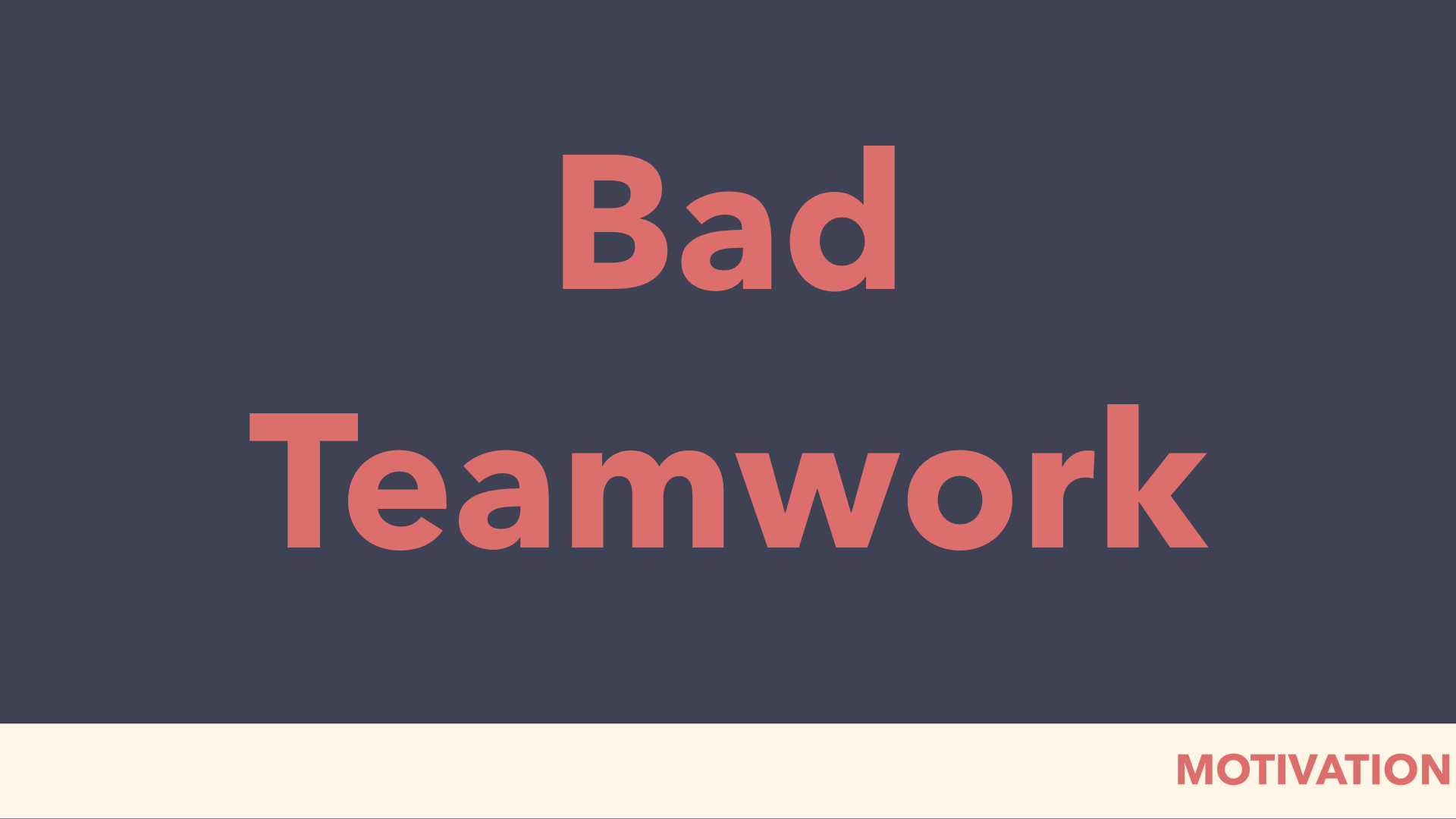
当たり前のことではありますが、みんなが頑張っているのに、一人だけ、サボってる人がいると、チームワークは悪くなってしまいます。
その原因は不公平感です。
なんで自分はやっているのに、他の人はやっているのに、あの人だけやってないのか?!という不公平感が生じます。
さらに、サボっていることを評価者である上司が見ていなくて、評価に反映させてなかったり、見ていたのに評価に反映されていないことがわかると、不満はどんどん貯まっていき、いつか爆発します。
全員が怠けていて、一人だけ頑張っているのであれば、すごいねと皆に見られて終わりなのですが、一人だけ怠けていると非難されます。
どうしてチームには怠ける人がいるのか?

怠ける人と怠けない人に違いはあるのでしょうか?例えば、責任感です。
怠けない人は責任感が強い!
怠けない人は責任感が強くない!
多くの場合は、責任感を感じない、もしくは弱くなってしまう事が原因です。
責任感を感じにくくなる原因が、集団にあります。集団で同じ作業をする場合に誰がどれだけやったのか?という結果がハッキリと分かる状況でない時に、怠ける人が発生します。
集団の利益よりも自分の利益を優先してる状態が発生していると言えます。
これを、社会的手抜きといいます。
社会的手抜きが発生する原因は5つ

社会的手抜きが発生する原因は、5つあります。
- 評価可能性
- 努力の不要性
- 手抜きの同調
- 緊張感の低下
- 注意の拡散
社会的手抜きの原因 〜評価可能性〜

評価可能性というとわかりにくいですが、簡単に言うと、
「やってるかやってないかがバレない」状況の事です。
わかりやすい例えだと、学校のクラス対応の綱引きや、応援です。
綱引きは、誰がどれだけ力を入れているのか?どれだけ貢献しているのか?がわかりません。
同様に応援も同じです。誰がどれだけ声を出しているのかわかりません。
個人の努力が評価できない状況は社会的手抜きが生じてしまいます。つまり無責任になる人が出てきます。
社会的手抜きの原因 〜努力の不要性〜

努力の不要性は何かというと、他の人たちが優秀であるがために。自分の努力が集団全体の結果にほとんど影響しない場合です。
そして、それでも集団の目標が達成されることが明確な場合です。
例えば、100本の2Lペットボトルを55人のチームで一人づつ運ぶ時に、最初の10人が頑張って4本づつ運んだ場合、すでに15本しか残らないので、残りの45人が1本づつ持っていこうとしても、ペットボトルの数が足りないです。
そういうことに早い段階で気づいている人ははじめから、自分がやらなくてもいいと決めてなにもしないようになります。
社会的手抜きの原因 〜手抜きの同調〜

他の人が頑張っていないつまり、社会的手抜きになってしまっているのに、自分だけが頑張っているのが馬鹿らしくなります。
その状況を手抜きの同調といいます。
悪い影響はすぐに広がるといいますが、まさにその例えですよね。
社会的手抜きの原因 〜緊張感の低下〜
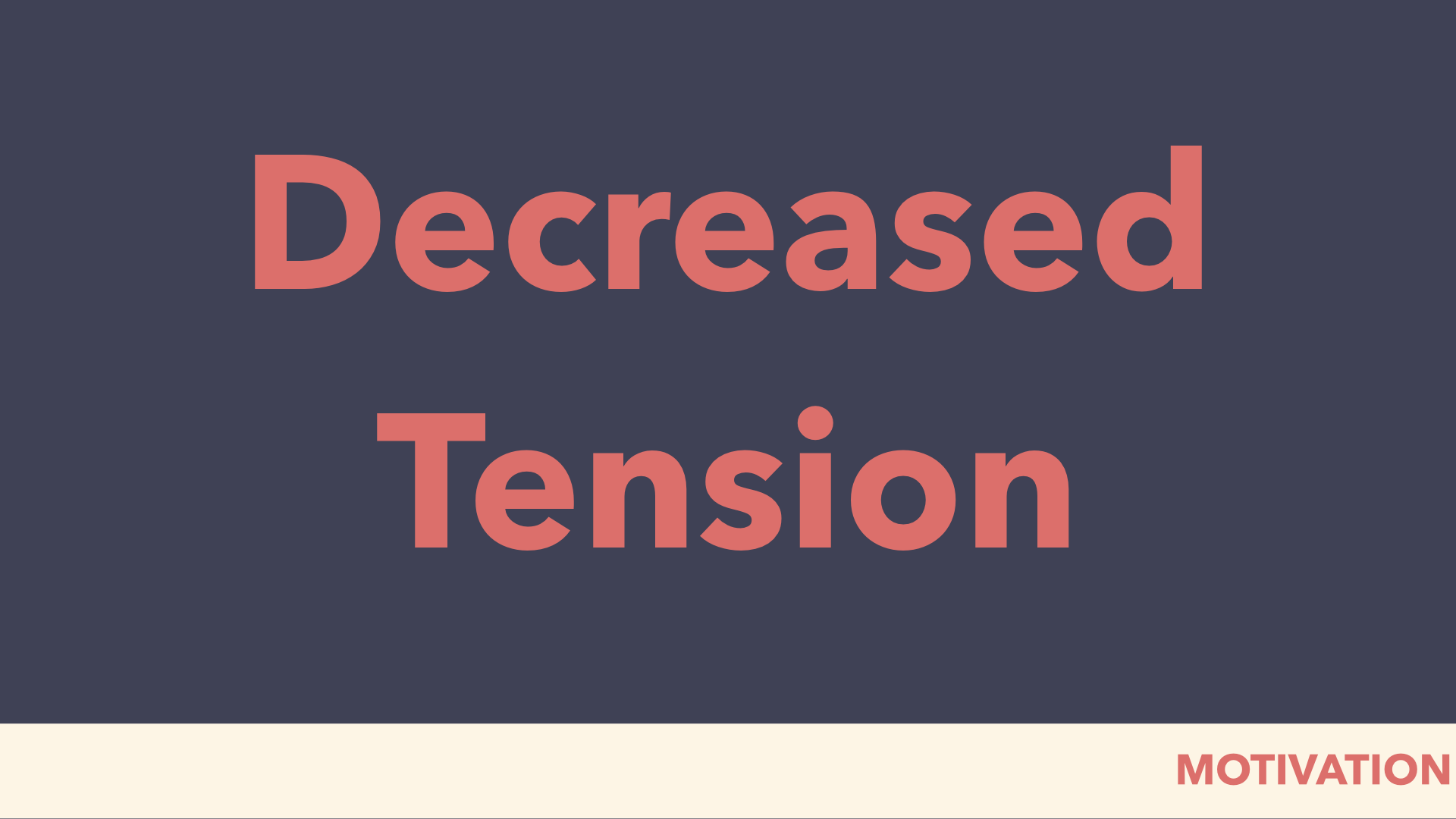
緊張感の低下が、手抜きに繋がる理由ですが、例えば、自社の商品をあるイベントで登壇して、一人でプレゼンしなければいけません。というケースは入念に準備をして、成功するように努力します。これは緊張感が高いからです。
では、展示会で自社のブースを出してました商品説明の要員は15名居ますとなった場合は、準備を怠る人が出てきます。
すくなくとも最初の一人でプレゼンするのと同じくらい準備をする人は少ないでしょう。
これが緊張感の低下がもたらす、社会的手抜きです。
社会的手抜きの原因 〜注意の拡散〜

注意の拡散は、自分への注意を意味します。先程の緊張感の低下の例で考えると、一人でプレゼンする場合は、注意はプレゼンしている自分に集中します。
でも、展示会で15名説明員がいるような場所では、自分に注意が集中することはほとんどなく、あらゆるところに注意が拡散します。
この状態を注意の拡散と言います。
社会的手抜きがもたらす負の効果
腐ったりんご効果
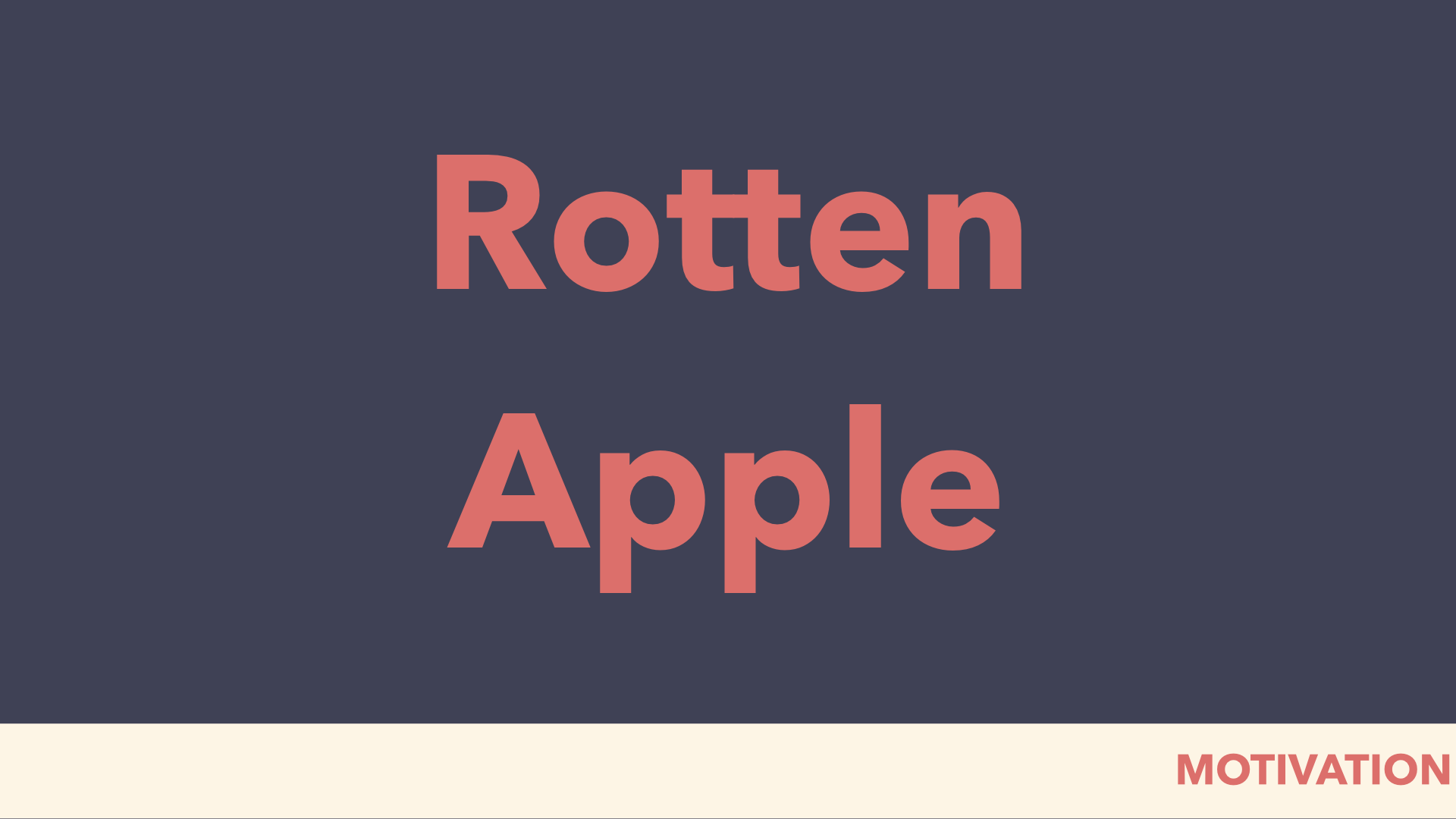
社会的手抜きにより、チームの中に一人でも手抜きをしている人がでてきます。
つまり、集団の利益よりも自分の利益を優先する人間が利己的な振る舞いをし始めます。
すると、その影響はすぐさま集団全体に広がり、結果として集団全体を利己的人間の集まりにする可能性があります。
社会的手抜きを防止する方法は9つ

集団にとっていいことなしの、社会的手抜きですが、それを防止する方法は学術的に9つあります。
- 罰を与える
- 社会的手抜きをしない人物を選考する
- リーダーシップにより、集団や仕事に対する魅力の向上を図る
- パフォーマンスのフィードバックを行う
- 集団の目標を明示する
- 個人のパフォーマンスの評価可能性を高める
- 腐ったりんごを排除し、他者の存在を意識させる
- 社会的手抜きという現象の知識を与える
- 手抜きをする人物自体が役割と捉える
ここでは、「2.社会的手抜きをしない人物の選考」と「8.社会的手抜きという現象の知識を与える」、「9.手抜きをする人物自体が役割と捉える」
社会的手抜きを防止する方法 社会的手抜きをしない人物の選考

社会的手抜きをしやすい人と、しにくい人の特性が研究によって明らかにされています。はじめからそういう人を選考して採用していれば、社会的手抜きが発生しにくいということです。
達成意欲がたかく、勤勉で、調和を重んじ、外向性があり、でも、ナルシストな一面をもち、自分を特別だと思いたい!
さらに、情緒が安定していて、他社に認識されたい!という欲求を持つ人です。
すぐに採用できそうな人ですね!笑
さすが、学術的な対策・・・・全てに適応している必要はありませんが、そういった要素を持っている人が影響されにくい事は確かです。
そういった人をリーダーや、重要なポジションを任せる選考基準という意味ではよいと思います。
社会的手抜きを防止する方法 社会的手抜きという現象の知識を与える

チーム全員に、「社会的手抜き」という集団心理が働いてしまうことを説明してしまうということです。
これは非常に効果があります。お互いに突っ込ませることができるからです。「社会的手抜きになってない?」とか、「今手抜きした?」とかそういったツッコミです。
社会的手抜きを集団が理解することで相互に防止することができます。
社会的手抜きの略語を作って言いやすくするのがよいでしょう。「シャテキ」とか、「シャヌキ」とか。
社会的手抜きを防止する方法 手抜きをする人物自体が役割と捉える

どんな対策をとっても、ずっと社会的手抜きにだれもはまらないようなチームは存在しません。一時的には存在すると思いますが、継続的に何年も誰一人いないということは考えにくいです。
そんな事は発生していない!と言い切ることができるチームは素晴らしいですが、そういった人が退職している可能性もあります。
チームである以上、社会的手抜きが発生すると考えた場合に、「社会的手抜きになった人にも、それを周りに認識させる役割がある」と捉え直す事ができます。
つまり、チームが理想的な状態で機能していれば、社会的手抜きは発生しないけど、社会的手抜きになった人が発生しているということは、チームに何か課題や問題点あるという考え方です。
チームの課題を指摘する為に、社会的手抜きになってくれる人がいて、その原因をなくすことでより活発に活動できる組織になれる!ととらえれば、社会的手抜きに陥る人が必ずしも悪いとは言えないと思います。
社会的手抜きを防止する シンプルな方法!
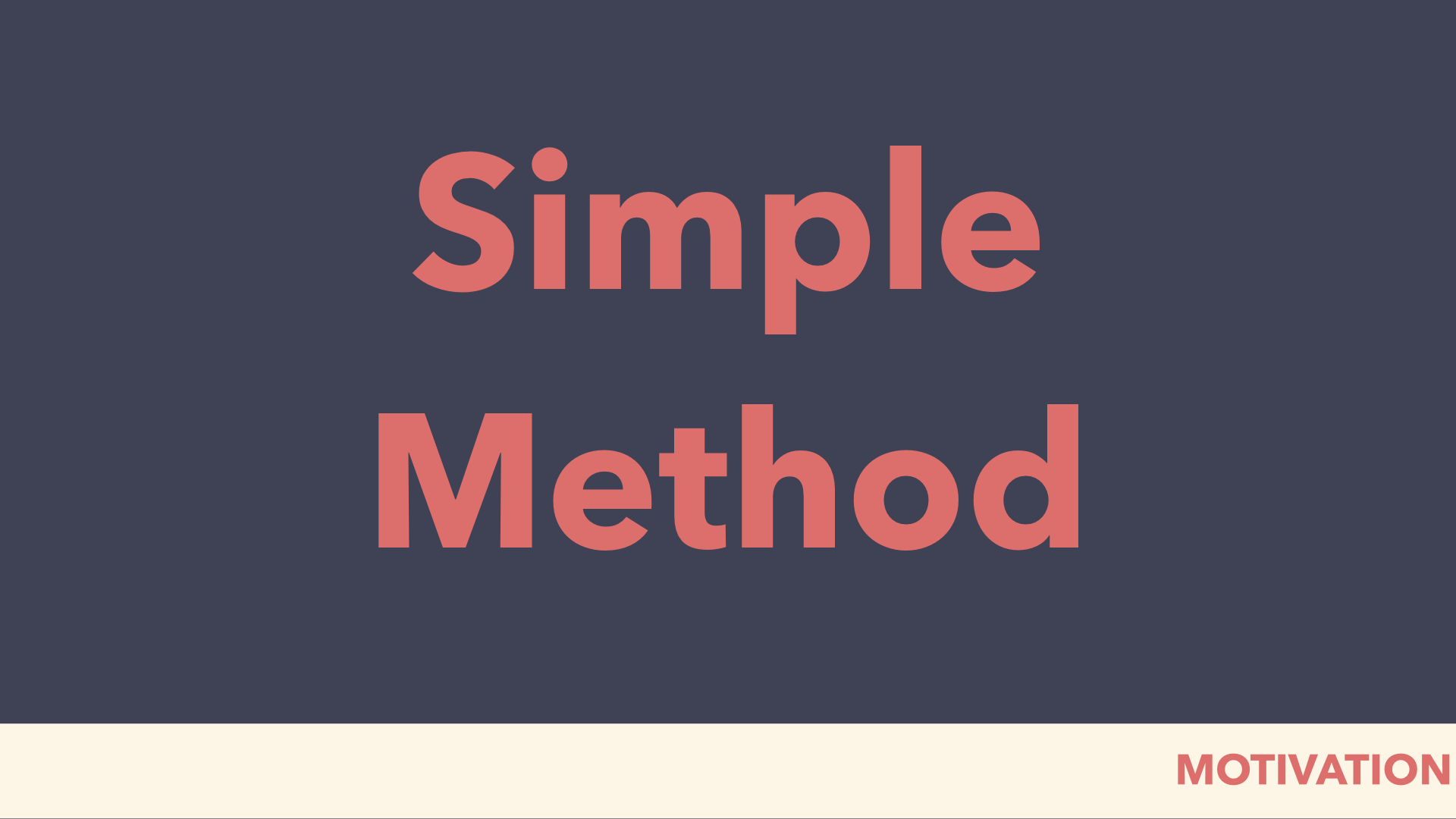
学術的には上記9点が対策になります。実践的なシンプルな解決策は3つあります。
- チームを小さくする
- 責任を明確にする
- チームメンバーへの好意の醸成(申し訳なさの醸成)
社会的手抜きを防止する チームを小さくする

社会的手抜きはチームが大きくなれば、大きくなるほど、発生しやすくなります。逆に、小さなチームでは手を抜いている事がすぐにバレるので、発生しにくいです。
その為、できるだけ小さい組織に分割します。目標と役割を分けることができるのであれば、リーダーを含めて5名以下が望ましいです。
社会的手抜きを防止する 責任を明確にする
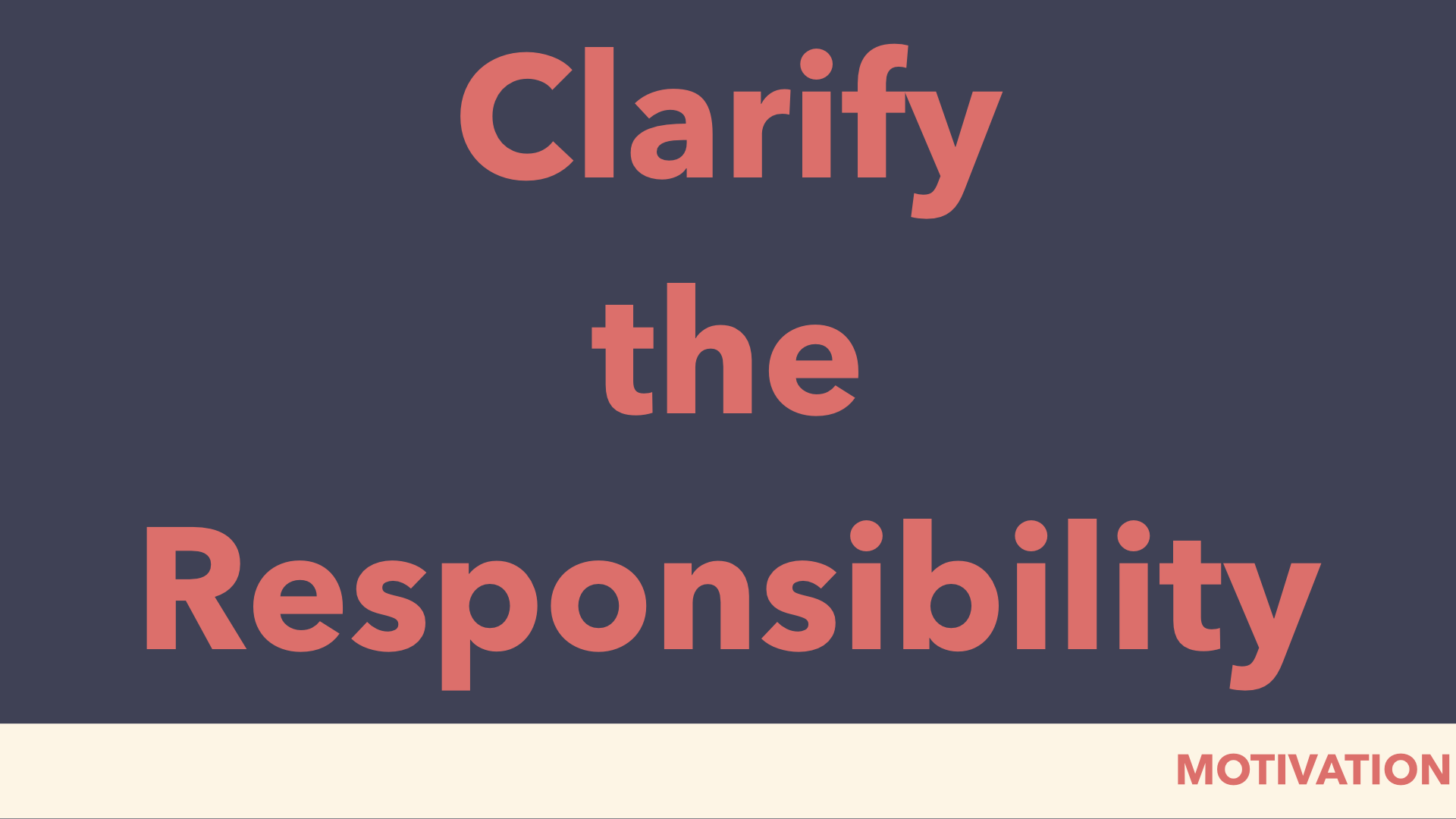
責任の範囲がわからない状態にしないことです。5人で1つの作業を完了させてください。というような指示になると、社会的手抜きは発生しやすくなります。
分割できる作業であれば、できる限り分割して、責任を持つ人間の数を減らします。そうすることで責任が明確になるので、どこまでだれがやったのか?もさぼったのかもわかりやすくなります。
その状態では、社会的手抜きは発生しにくいです。
社会的手抜きを防止する チームメンバーへの好意の醸成(申し訳なさの醸成)

チームメンバーへの好意の醸成(申し訳なさの醸成)というのは、自分が手を抜くことで誰かに迷惑をかけてしまう。
あの人に迷惑をかけるのは申し訳ないからちゃんとやらないと!というような意識をもたせる事です。
分割できない作業で、個人の責任が明確にならないケースにこれを考慮して役割を分担すると社会的手抜きは発生しにくいです。
みんなから好かれている人や尊敬されている人、恩を感じている人が多い人などと手を抜きやすい人をセットにしてしまうのです。
社会的手抜きのまとめ

人間が集団を形成する時には、1人の時とは異なる、集団心理が働きます。コレによって良い影響もでれば、悪い影響もでます。
それを理解し、良い影響を増やし、悪い影響を減らすかは、メンバー個人のチカラも必要ですが、人を見抜き制度を整えるマネジメント側の力量によるところが大きいです。
社会的手抜きを知ることで、個人のしての成長にも繋がります。社会的手抜きに陥ると成長できません。それに気づきましょう!また、腐ったりんごになっている人にも気づけるはずです。同じように腐らないようにしましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。この記事が少しでもお役にたてば幸いです。
この記事が役に立った方にオススメの記事
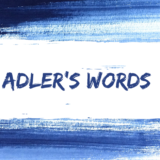 モチベーションに繋がる言葉!やる気にさせる心理学!アルフレッドアドラーの36の名言!【モチベーション】
モチベーションに繋がる言葉!やる気にさせる心理学!アルフレッドアドラーの36の名言!【モチベーション】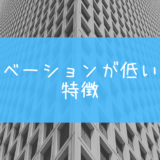 モチベーションが低い人の特徴は?もしかしたら、心の病気になってるかも心も風邪ひきます
モチベーションが低い人の特徴は?もしかしたら、心の病気になってるかも心も風邪ひきます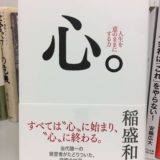 書評『心。人生を意のままにする力』要約・レビュー (著者:稲盛和夫)
書評『心。人生を意のままにする力』要約・レビュー (著者:稲盛和夫) 人生が楽しくなるオススメ本、人生を変えた厳選5冊
人生が楽しくなるオススメ本、人生を変えた厳選5冊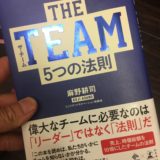 書評『THE TEAM 5つの法則』要約・レビュー (著者:麻野耕司) 第1章・第2章
書評『THE TEAM 5つの法則』要約・レビュー (著者:麻野耕司) 第1章・第2章 チームワークの良い職場の作り方・社会的手抜きの原因と対策
チームワークの良い職場の作り方・社会的手抜きの原因と対策
 Simple WORK
Simple WORK 



